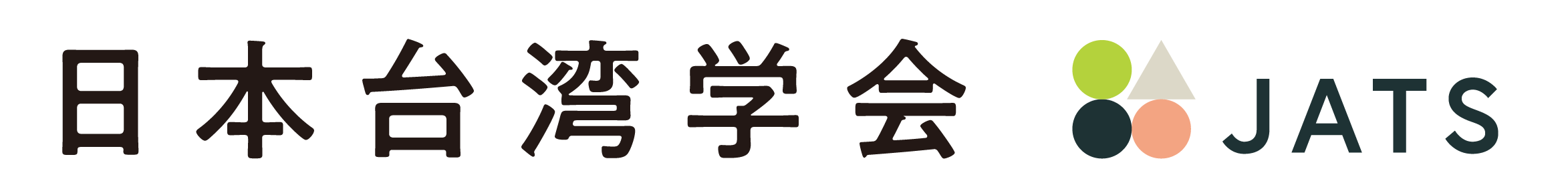日本台湾学会台北定例研究会
第22回
司会
| 日時 | 2004年3月21日(日) 18:30-20:30 |
| 場所 | 国立台湾大学 哲学系館 一階の大会議室 (台北市羅斯福路四段1号) |
| パネラー | 頼 怡忠 氏(台湾智庫国際事務部主任) 渡辺 剛 氏(杏林大学) 松田 康博 氏(防衛研究所) |
| 佐藤 幸人 氏(アジア経済研究所) | |
| 使用言語 | 北京語が中心 |
| 参加費 | 会場費として1人50元 |
| テーマ | 「綜觀2004臺灣的総統大選――公投・制憲・族群・地域(南北)」 |
参加体験記
大統領選挙翌日の3月21日に、台湾大学で第22回台北定例会がおこなわれた。もちろん話題は大統領選挙であり、松田康博氏(防衛研究所)、頼怡忠氏(台湾智庫国際事務部主任)、渡辺剛氏(杏林大学)をパネラーに迎えての例会は、参加者も40人あまりを数え盛況であった。テーマは「綜觀2004臺灣的総統大選-公投・制憲・族群・地域(南北)-」だったが、投票日前日には陳・呂候補に対する銃撃事件、さらに選挙の大勢があきらかになってからは、連・宋候補による選挙無効の訴えと、人々の予想をはるかに超えるであろうできごとが発生し、定例会の議論はさまざまな方向に広がった。したがって、以下で全般的な内容を網羅することは不可能であり、報告から抜け落ちてしまう部分がかなりあることをあらかじめお断りしておきたい。当日は、司会の佐藤幸人氏(アジア経済研究所)の進行のもと、まずそれぞれのパネラーによる20分ほどのコメント、続いてパネラーの間での質疑応答、さらに会場とパネラーの間での質疑応答という流れで議論が進行した。まずパネラーのそれぞれの発言のうちのいくつかを、簡単に箇条書きでまとめる。
渡辺氏
・ 今回の選挙で顕著だった泛緑の北部での票の伸長は何を意味するのか。
・ 銃撃事件によって、泛緑陣営が危機感を高めた、あるいは普段は投票には行かないであろう人々が投票所に向かったということはあったのかもしれないが、いわゆる「中間選民」の投票行動にはそれほど大きな影響を与えなかったように思う。
・ 選挙無効運動が展開されることになった背景には、元来の泛藍支持層の一部が今回の選挙で泛緑に流れたとみられることに対する危機感、また、政府攻撃の材料を確保しておきたいという意図があるのではないか。
松田氏
・ 選挙後の連宋の動きは、敗戦の責任を国親連合のあり方などみずからの側にではなく他に求めようとしており、これは今後の国民党、泛藍にとってマイナスに働くだろう。
・ 有権者の過半数が投票しなければ成立しない現在の公投法の規定はハードルがあまりにも高すぎるので、ある程度条件を下げなければ今後も成功は難しい。
・ 泛緑の勝利によって、すぐに中国との関係に変化が起こるということはないだろう。今後は両者の間で、どのように対話のための雰囲気を醸成していくのかということが重要な課題となる。
頼氏
・ 連宋は敗戦そのものは認めているのではないか。大統領府前での抗議行動も、一見藍緑の対決に見えるものの、実際には泛藍内部のつばぜりあいだろう。
・ 親民党は泡沫化を心配し、連宋支持の中心になっている。国民党の今後の対応いかんでは、年末の国会議員選挙で泛藍票のかなりの部分が親民党に流れる可能性がある。
・ 公投法を機能させるためには修正が必要だ。今後の制憲議論のなかで公投をどのように位置づけていくかということが国会議員選挙の行方ともからんでくる。
・ 陳政権の外交政策(とくに対米、対日政策)にとくに変化はない。ただ米国の大統領選挙で民主党が勝利した場合、米国の政策は対中関係をより重視したものになるだろう。
その後は、たとえば泛藍の選挙後の戦略は果たしてどれだけの有効性を持っているのか、国会議員選挙の候補者決定までのプロセスにおいて、緑藍間で候補者の乗りかえが起こる余地がまだあるのかいなか、選挙戦中にもその投票行動が注目された「中間選民」なるものはそもそもどのような存在なのか、などといったことが話題になった。また、選挙の重要な争点の一つと思われがちな経済政策は、実はそれほど大きな要素にはなっていないのではないかという指摘は興味深かった。
定例会からほぼ10日が経過した本稿執筆時には、選挙結果がくつがえるかもしれないという雰囲気はもはやほとんどなく、粛々と陳政権2期目に向けての準備が進行しているように感じられる。ただ、討論でさかんに取り上げられた泛藍の今後の方向性については、いまだはっきりとした姿は現れていないようだ。
今振り返ってみて、私自身、当日は何かしら気もそぞろであった。しかし、専門的な立場から選挙を観察してこられたお三方の見方や熱のこもった議論は、この数か月の間の激しい選挙戦や今後の政局に対して、素人的にではあるが、冷静にあれこれ思いをめぐらすことを可能にしてくれたように思う。もっともその後の1週間は、やはり落ち着かない非日常を過ごさざるをえなかったのであるが。 (冨田哲 記)