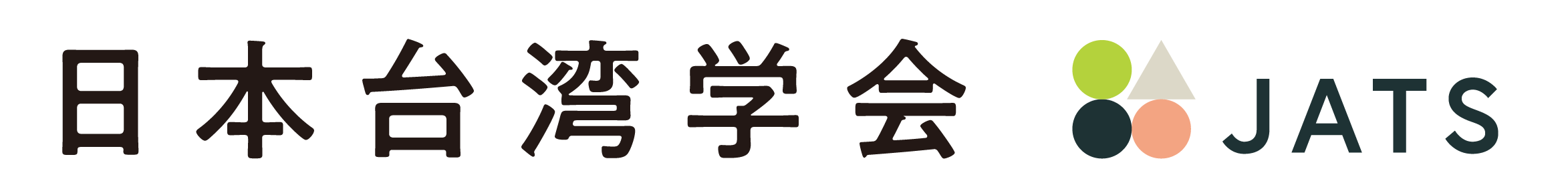最終更新:2025年9月29日
第14期理事長就任にあたって
川上桃子(神奈川大学)
このたび、日本台湾学会第 14 期理事長に就任いたしました。本学会は、1998年の設立大会以来、日本における学際的な地域研究としての台湾研究を志す研究者のネットワーク構築および他地域の台湾研究との交流を主な目的として、歩みを重ねてきました。この道のりを思うとき、このたびお引き受けした責任の重さに緊張を覚えます。
幸い、本学会の活動は、学術大会、学会報、ニュースレターの「三点セット」に加え、定例研究会、ウェブサイト等を柱として、安定した軌道に乗り、活動のリズムを着実に刻みつづけています。また本学会には、専門や世代を異にするメンバーがチームを組んで仕事をするという伝統が長く根づいています。14期常任理事会でも、学会活動の活性化にチームで取り組んでいきたいと思います。
本学会が産声をあげた1990年代後半、日本の台湾研究者たちを悩ませたのは、日本社会における台湾への無関心、台湾を独立した研究対象とする学術活動への無理解、そして台湾に対する植民地支配責任をめぐる研究者としての葛藤であっただろうと思います。それから約30年を経て、日本では今、流動化し緊迫する東アジアの国際情勢のもと、台湾への関心がかつてなく高まっています。同時に、台湾をめぐる議論が時に極論に走ったり、過度に感情的になったりする状況もしばしば目にします。台湾でも政治的対立の深まりへの懸念を耳にすることが増えました。
こうした状況だからこそ、台湾をめぐる学術研究のプラットフォームとしての本学会の役割は重要です。心理的安心感がもてる環境があってこそ、建設的な相互批判を通じて、多様な知識を生み出し、台湾に対する理解を広げ、深めていくことが可能になります。
第14期常任理事会では、先輩方が守ってこられた本学会のアカデミックな伝統を大切に継承していくと同時に、活動の実務面での改革を積極的に進めていきたいと考えています。まず、デジタル化の取り組みとして、役員選挙への電子投票の導入、学会報のJstage搭載、ニュースレターのデザイン改定を進めます。
あわせて今期は、会員による各種学会業務のありかたについても再検討する予定です。本学会に限らず、日本の学会では、学会の各種業務が会員のボランティアで行われてきました。しかし、学会が発展すれば、各種の業務はおのずと増加します。こうした業務をどのように分担していくのか。多忙ななかで学会活動の縁の下の力持ちを引き受けてくれる中堅・若手会員の貢献にどう報いていくか。これまでの学会の慣習にとらわれず、議論すべき時期を迎えていると考えます。
進取の気風とフットワークの軽さが本学会の身上です。次の10年、20年を見据えた学会活動の持続性を意識して、活動面での創意工夫を重ねていきたいと思います。会員の皆さまにはどうぞよろしくご理解、ご協力のほど、お願い申し上げます。