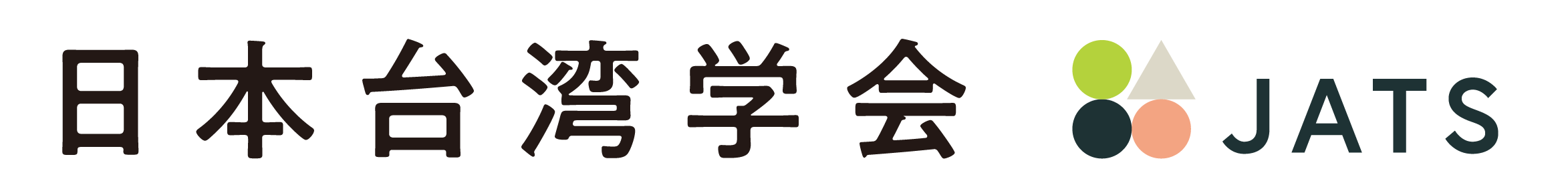最終更新:2011年6月5日
台湾研究の可能性
—理事長就任の挨拶に代えて—
第7期理事長 山口 守(日本大学)
振り返ればもう13年前になりますが、日本台湾学会設立大会(1998年5月30日、東京大学本郷キャンパス)において「“台湾研究”とは何か?」と題したシンポジウムが開催され、文学部門のパネリストとして登壇した時の会場の熱気がいまだに忘れられません。空調設備のない会場が暑かったのは確かですが、その時、その会場に参集した人々の台湾研究に対する熱意が大教室に充満しているように感じ、壇上にいた私もその熱気に押されるように夢中で話をしました。あの当時、台湾研究は必ずしも固有の学術研究として日本社会の中で広く認知されていたわけではありませんが、そのことよりも、学会の出発点にあたって、自らの学術研究の立場と方法論を真摯に問う姿勢に、新しい研究空間が生まれつつあるという実感と感動を覚えました。台湾研究に対するその精神や熱意が、現在に至るまで継続されていることが、この学会の特徴であり、また魅力だと思います。
あの時パネリストとして私は「多元性を持った台湾文学の研究に潜んでいる新しい理論創造への希望」(「越境する文学と言語」『日本台湾学会報』第一号)に言及しましたが、その考えは今でも変わりません。台湾研究には、既成の学問研究を乗り越える新たな理論創造の契機が常に存在し、それが形になる可能性が秘められています。私自身は文学研究者ですが、台湾文学を研究するならば、言語、歴史、人類、政治、経済など様々な関連分野に越境して学習し、新しい学術言説の枠組みを構築する必要が生じます。或いは日本、中国、朝鮮、アメリカなど、参照する地域を越境していかないと研究が進みません。恐らく他の分野でも同じだと思いますが、自分の学問領域に依拠しながらも墨守しない開放性と、国家や民族の固有性神話を乗り越えて越境する自由度の高さが、台湾研究の特徴であり、またこの学会の発展の方向性でもあると思います。
また、今年早稲田大学で開かれた第13回学術大会記念講演で、ベネディクト・アンダーソン教授が地域研究に必要なemotional attachmentについて語りましたが、中でもshame and painの自覚が必要であるとの言葉に、私は深く感銘を受けました。台湾研究に引き付けて言えば、それに愛着を感じるならば、常に自らの研究の不足や欠点を恥じる意識を保つことが大切であり、また研究対象とする台湾の社会や人々の痛みへの想像力を欠いてはならないということです。長い異民族統治下で苦しむ原住民の人々、半世紀に及ぶ日本の植民地統治によって流れされた夥しい血と涙、冷戦体制と戒厳令にも関わらず果敢に自由と民主を求めた人々の苦闘、そうした台湾の社会や人々の痛みを深く理解することなしに、台湾研究を行うことはできないのです。今回の地震被害・原発事故に際して、台湾の人々が百数十億円もの義捐金を送ってくれた優しさの背後に、そうした苦痛の歴史があることを忘れることはできません。
日本台湾学会も今や会員数が500名を超える規模となりました。学術的公共空間に相応しい運営体制の充実が今期の課題のひとつですが、春山明哲前理事長を始めとして、これまで各理事長が築いてきた基盤に拠りながら、透明度の高い学会運営を目指していきたいと思います。学会員のみなさんの積極的な学会活動参加、並びにご意見、ご批判がその透明度を高めます。2年間の任期中、どうぞよろしくお願いいたします。