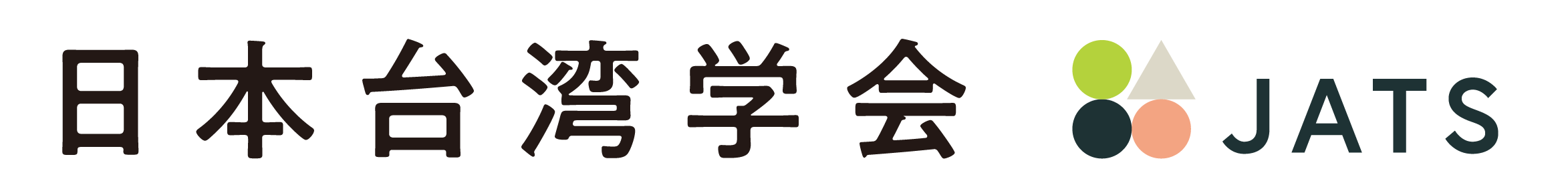日本台湾学会台北定例研究会
第45回
| 日時 | 2008年3月15日(土) 15:00開始 |
| 場所 | 台湾大学台湾文学研究所220室(閲覧室) (台北市羅斯福路四段一号) |
| 報告者 | 安達 信裕 氏(広島大学大学院社会科学研究科博士後期課程) |
| テーマ | 「植民地期台湾の公学校における台湾語の利用について」 |
| 使用言語 | 日本語 |
| コメンテーター | 陳 培豊 氏(中央研究院台湾史研究所) |
参加体験記
2008年3月15日に台湾大学台湾文学研究所で第45回台北例会がおこなわれた。報告者は安達信裕氏(広島大学大学院社会科学研究科博士課程後期)、コメンテーターは陳培豊氏(中央研究院台湾史研究所)で、13名の参加があった。
報告のタイトルは「植民地期台湾の公学校における台湾語の利用について」。公学校教育の教授言語として台湾語がどのように使用されていたのか、そしてそ れは時期的にどのように変化していったのかを実証的にあきらかにしようというこころみであった。まず概要を以下にまとめる。
公学校においては日本語の教育が中心であり、教授言語も日本語のみとされる場合が多かった、かりに台湾語が使われたとしても、それは「国語」教育のため の補助的手段に過ぎなかったと、一般的には理解されている。しかし、1910年代には低学年の修身の授業などは台湾語でおこなわれるのが普通だったようで ある。児童に内容を十分に理解させるためには台湾語の使用が必要であるといった意見が公学校長や教師からも表明されている。しかし1920年代後半あたり には教授用語としての台湾語を否定する意見もあらわれるようになる。台北第三高女主催の修身教授についての研究会の資料には、法規的あるいは教育的な観点 から主張された賛否両論が掲載されている。結局、学校においては日本語を使用すべきであるという原則論が力を持つようになり、教授言語のみならず学校内で の台湾語使用までもが批判の対象となっていく。さらに、台湾語を使わなくても可能な教授法も提案・実践されるなど、学校内における「国語常用」への動きが強まっていった。
こうした一連の変化は、台湾人教員と日本人教員のあいだの力関係にも大きな影響をあたえたのではないかと推測できる。台湾語が修身の教授言語でなくなる ことで、それまでの台湾人教員が優位に立っていた空間が日本人教員のコントロール下に置かれるようになっていったのではないだろうか。
以上の報告に対して、陳氏は次のようなコメントをおこなった。日本統治期に台湾人に「忠君愛国」などを教えようとしたとき、それを日本語でおこなうとい うのは非常に非効率的ないとなみだったはずである。しかし、日本語の使用と日本人への「同化」を単純に一体化させる議論に、台湾語を使わなければ修身の教 授内容を理解させられないといった声はかき消されることになった。このような教育現場からの訴えには、植民地における「二言語併用」の問題を考察するため の手がかりもつかめそうだが、こうした観点は今日にいたるまでの台湾における言語と政治、言語と「近代性」の問題への示唆をも含むものだろう。
紹介された台湾語使用の是非についての討論で話題になっているのは、「台湾語」であり「漢文」ではない。たとえば統治初期の漢文教育論争から浮かび上が る漢文のハイブリッド性などを参照することで、当時の台湾語と漢文の位置に対する視点も開けてくるのではないか。
以上を受けての質疑応答では、各時期の資料が検討されているが、同時期の台湾総督府の文教政策との対照によって台湾語利用状況の変化をよりくわしく描き 出せるのではないか、教育関係者の主張や日本人/台湾人教員数の割合の推移にとどまらず、それらがどのように言語使用の実態に影響したのかに踏み込む必要 がある、日本人教員の議論を台湾人教員はどのように見ていたのか、公学校教師はそもそも「台湾語」と聞いてどのような対象をイメージしていたのか、それと 「漢文」とはどうかさなりあっていたのか、といった論点が提示された。
今回の議論では、一口に「台湾語」と言ったときにそれが音声言語をさすのか、それとも漢文までをも含むのかという、日本統治期台湾の言語の問題を考える うえで非常に重要かつ複雑な問題が浮かび上がった。安達氏があきらかにしようとしている教育現場における台湾語の使用は、「国語」教育にかんする研究のか げに隠れてこれまであまり論じられてこなかったものであり非常に興味深かったが、日本統治期の漢文の問題をめぐる近年の意欲的な研究の成果も参照することで、より時代の文脈にそくした考察が可能になるのではないかと感じた。(冨田哲記)