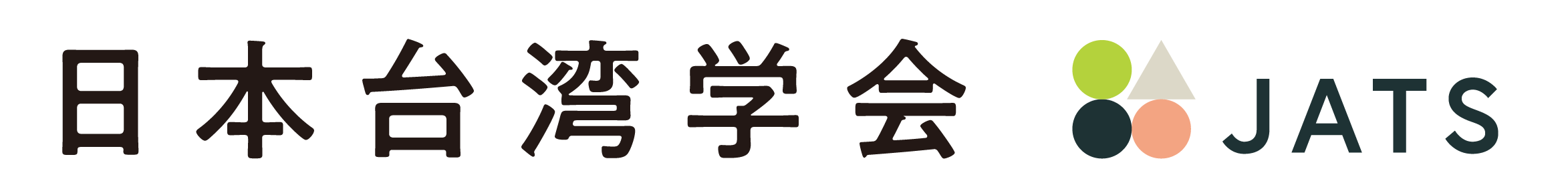日本台湾学会台北定例研究会
第48回
| 日時 | 2008年12月20日(土) 15:00開始 |
| 場所 | 台湾大学台湾文学研究所220室(閲覧室)(台北市羅斯福路四段一号) |
| 報告者 | 春山 明哲 氏(日本台湾学会理事長、政治大学台湾史研究所客座教授、早稲田大学台湾研究所客員研究員) |
| テーマ | 「日本における台湾研究の最近の動向と今後の展望」 |
| 対話人 | 張 隆志 氏(中央研究院台湾史研究所) |
| 使用言語 | 日本語・北京語 |
| 参加費 | 無料 |
参加体験記
2008年12月20日に台湾大学で、22名の参加者を集め第48回台北例会が開催された。9月から12月まで政治大学台湾史研究所に客員教授として滞在していた本学会理事長の春山明哲氏(早稲田大学)が、「日本における台湾研究の最近の動向と今後の展望」と題して報告をおこない、それを受けて「対話人」の張隆志氏(中央研究院)が台湾史研究の動向について発言をおこなった。
春山氏の報告は、第10回学術大会記念シンポジウムでの基調報告(「日本台湾学会の10年を振り返って」)とパネルディスカッション(「台湾研究この 10年、これからの10年」)の概要紹介、および今回の台湾滞在中の観察が中心だった。内容は以下のとおりである。
1998年の設立大会の際、若林正丈氏は司会者冒頭発言で「台湾研究」のイメージ(『日本台湾学会報』第1号所収)として、地域研究の対象としての台湾の濃厚な個性、台湾研究の二重の学際性、開放的な台湾研究の必要、研究の実践的指針としてのリベラリズムとプラグマチズム(国民国家パラダイムやナショナリズムを相対化する一方で、台湾研究の発展のためにはイデオロギー闘争の場からも積極的に知見を取り入れるべき)、の四点を提示した。このうち、とくに一点目と二点目を参照しつつ、10年間の日本における台湾研究の動向をつかむために、『日本台湾学会報』の論文154本、および学術大会報告者論文集の報告 79本の計233本の分析をおこなった。具体的には各研究を、主題から「政治・経済・歴史・社会・文化・文学・教育」の7項目、対象とする時代から ①1895年まで(清朝期)、②1895~1945年(日本統治期)、③1945~1986年(戒厳令解除まで)、④1987年から現在、の4期のいずれかに分類した。
その結果、どの主題にもほぼ②、③、④各期の研究が見られ(ただし①の時期の研究は僅少)、台湾研究の歴史の重層性は顕著であった。上記各主題の分類とは別に抽出した「原住民」関連の論文についても同様である。一方、主題をいずれか一つのカテゴリに分類することには大きな困難をともなったが、まさにこれこそが台湾研究の学際性を傍証するものであろう。
ここでいう学際性とは、学問的ディシプリンの横断を意味しているが、くわえて「領域際的」とでも言うべき傾向も顕著である。たとえば233本の研究のうち、文学に分類されるものがもっとも多く61本を数えるが(うち②の時期が43本)、設立大会での山口守氏の報告タイトル「越境する文学と言語-中国文学・台湾文学・日本文学」にあるごとく、台湾文学研究の学問的アイデンティテイに対する問いは、研究者を領域際的な場へと導いていかずにはおかない。
なお領域際的ということでいえば、台湾人による研究が全体の三分の一、また学会賞受賞論文の半分を占めており、日台間の学術交流の活発化、深化を反映している。日本台湾学会の学術団体としてのアイデンティティの所在ともかかわる特筆すべき特色であろう。
続けて、下村作次郎氏の基調報告の紹介、パネルディスカッションの概要紹介があったが、これらについては、学会ニュースレター第15号の滝田豪氏による詳細な報告にゆずりたい。
最後は「台湾で考えたこと」であった。政治大学台湾史研究所での講義以外にも、中央研究院、国立中央図書館台湾分館、複数の大学、読書会などでの講演、研究者との対話、さらには春山氏自身の台湾の親戚のことなど、密度の濃い台湾滞在の日々が語られた。
張隆志氏の話は、例会の二週間ほど前に中央研究院台湾史研究所、政治大学台湾史研究所、台湾師範大学台湾史研究所が共催したシンポジウムでの報告の前半部分をもとにしたものであった。張氏は、「本土史学史」の観点から、80年代以降今日にいたる台湾史研究の動向を整理した。内容は以下のとおり。
ここで言う本土史学とは、外来の知識体系や主流学術理論を相対化しつつ、植民地統治や権威主義国家体制、有力エスニックグループに対する批判も志向する歴史研究のありかたである。その意味で、本土という概念は本来、みずからの歴史を語ることばの探求を要請するものであり、そうした努力が社会に解放をもたらす力ともなるはずである。
政治的自由化にともない、この20年ほどのあいだに大きな発展をとげた台湾史研究は、台湾という空間を研究の中心にすえつつ、一方で歴史知識の「民主化」にも取り組んできた。史料の発掘や整理、復刻出版やデジタル化により、台湾史に関心をもつ多くの人々が重要史料を共有できるようになっている。時代、ジャンル、理論面ではばが広がり、中央研究院や各大学での台湾史研究の制度化も進んだ。海外の台湾史研究者、研究団体との交流も活発になっている。
もっとも、今日の台湾史研究を論じようとすれば、80年代以前の歴史研究からの影響にも注意を向けないわけにはいかない。ここには、日本統治期の総督府の学術調査や研究者の著作を含む日本植民地史としての台湾史、第二次大戦後に台湾に持ちこまれた中国現代史料学派の伝統を引き継いだ中国地方史としての台湾史、欧米の研究者による地域研究としての台湾史、そして海外で反政府運動や台湾研究にたずさわった台湾人が語った台湾史、という四つの大きな流れがある。政治的立場のことなりとも密接にかかわる多様な歴史論述が折り重なる場として台湾史研究は展開してきた。
本土史学としての台湾史の研究は、中国史、日本史がその一構成部分として、あるいは欧米の地域研究が一フィールドとして台湾をとらえるのとはことなり、台湾という土地やそこに住んだ/住む人々の現実に対する痛切な関心に突き動かされるものである。80年代以降の学術機構を中心とした台湾史研究は、特定社会集団中心の史観を批判し、長い時間スパンのもと、台湾と東アジア各地域とのつながり、多様な生活経験や集団記憶に注目した研究をつみかさねてきた。学際性をそなえた研究の深化、また民間歴史研究者や団体、出版社、メディアなどの歴史論述への積極的関与は、これからも台湾史研究の重要な特色でありつづけるだろう。
ただ、以上のような研究のあり方の一つの帰結として、台湾史研究はたびたび、アイデンティティ・ポリティクスの論争の場にもなってきた。日本統治期について言えば、1984年の台湾現代化論争、1997年の『認識台湾』論争、2001年の『台湾論』論争があげられる。また90年代以降の政治状況のもとで、本来、社会の解放のための原動力であった「本土」という語が、単なる一政治言語へと変質してしまったことも指摘しておく必要がある。
春山氏は台湾研究全般、張氏は台湾史研究をテーマとしていたが、両者は「学際性」「超領域性」「重層性」といったキーワードによって呼応しあうものであった。開放的で懐の深い研究環境がいかに重要であるかということは、台湾という空間に真摯に向き合う研究者であればだれしもが感じていることであろう。台湾研究が狭義の意味での「政治」とつねにとなりあわせであることは否定のしようがないが、だからこそ、台湾社会の多様性を歴史的必然として受け入れること、そして台湾がたえず「外」の世界との物理的、精神的なかかわりのもとで存在し続けてきた事実を認識することは、いかなる領域の台湾研究においても必須である。報告後の討論でも話題になっていたが、相違する立場、研究視点、学問的ディシプリン、領域を大胆にのりこえていけるような思考、そしてそこに対話の可能性をさぐっていく姿勢こそが、まず台湾研究の大前提とならなければならない。(冨田哲記)