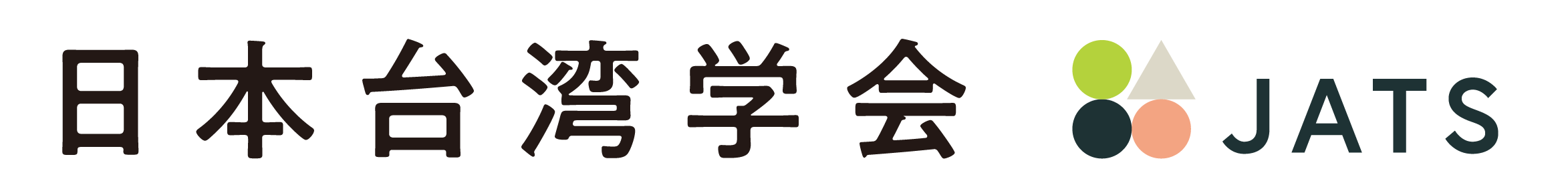日本台湾学会台北定例研究会
第49回
| 日時 | 2009年7月11日(土) 15:00開始 |
| 場所 | 淡江大学台北キャンパス D206室 (台北市金華街199巷5號) |
| 報告者 | 藤本 典嗣 氏(福島大学共生システム理工学類) |
| テーマ | 「民進党政権期における台湾の地域構造の変容-本社・支所立地の観点から」 |
| コメンテーター | 田畠 真弓 氏(東華大学社会発展学系) |
| 使用言語 | 日本語 |
参加体験記
2009年7月11日、淡江大学台北キャンパスで第49回台北例会が行われた。報告者は藤本典嗣准教授(福島大学共生システム理工学類)、コメンテーターは筆者の田畠真弓(国立東華大学社会発展学系)で、5名の参加があった。
報告のタイトルは「民進党政権期における台湾の地域構造の変容-本社・支所立地の観点から」。国営企業の民営化やハイテク産業の台頭、そして台湾企業の中国進出といった近年の変容が、台北市を中心とした一極集中型都市システムにどのような影響を与えるかを実証的に明らかにしようとする斬新な試みであった。以下、報告の概要をまとめる。
通常、先進資本主義諸国では民主化や中央政府権限の地方政府への移譲から経済機能の首都一極集中が起こりにくいというのが定説になっている。しかし、東アジア諸国の中で首都への一極集中が著しい国土構造が見られるのが日本、韓国、台湾等だという。対照的に、社会主義国家である中国の首都、北京は経済中心地から地理的に大きく離れている。経済機能の首都一極集中化という現象は、台湾社会のどのような背景から生まれ、今後どのような変貌を遂げるのだろうか。このような問題意識から、藤本教授は既存の台湾企業研究を回顧し、台湾企業の本社・支所の立地に着目した研究が欠落している点を指摘、マクロとミクロのギャップを埋め、台湾全土におけるオフィス立地構造や経済機能の台北一極集中がもたらす問題点について明らかにするというセミマクロ的な分析の枠組み構築に取り組んでいる。
日本の場合、上場企業の本社立地は首都東京に集中し、関西の本社立地は減少傾向にある。一方、台湾の事業所立地構造を見ると、北部の伸び率が相対的に低く、中部、南部において高い成長率となっている。また、上場企業のオフィス立地パターンでは電子業の上場企業が増加し、絶対数では台北市内に本社立地が集中しているが、その一方で新竹サイエンスパークが大きく成長している。さらに政治的な影響から見ると、民進党政権の誕生で党営企業のスリム化が進み、 2008年3月、国民党に政権交代してからもこうした「小さい政府」を目指す政策的なコンセンサスは維持されているため、2000年代以降、民営化の一層の推進で党営事業が縮小しつつある。藤本教授は、本社の台北集中は戦後の開発独裁のプロセスで、政治機関が集中する台北での国営企業の創業を促進したことによるものであり、民主化やグローバル化の進展を通じて立地構造が大きく変化しつつあると分析している。特にハイテククラスター(産業集積地)の果たした役割は大きく、2000年代以降、新竹サイエンスパークに代表されるような、政府機関と日常的な対面接触が困難な台北市以外の北部(新竹県市、台北県の中和や新店)という地理的条件において、民間のハイテク企業を中心とした本社の増加が見られるようになっている。新竹サイエンスパークのエレクトロニクス企業はそのほとんどが米国で理工学系、経営系の学位を取得して帰台した人材や公的研究機関(工業技術研究院等)の技術者が創業しており、開発独裁や党営事業との関連性は極めて低い。このことから、企業の創業・運営において台北市所在の政治及び行政機関の影響力が低下しつつあることが伺える。
こうした一連の変化をふまえて、藤本教授はさらに中国沿海部における台湾企業の立地行動と制度的諸要因についても言及した。米国、日本、韓国、台湾から中国に向けての生産工程の移転は、雁行形態論(赤松)、プロダクトサイクル論(バーノン)、多国籍企業論(ハイマー)等の枠組みから国民経済相互の産業構造の国際調整(低廉な労働力、中国市場の潜在力、産業集積を求めて進出する立地)という視点から論じられる場合が多い。しかし、藤本教授の分析によれば、中国における省別、都市別の産業立地における外資は、国別に偏向して分布しており、台湾企業の場合は制度的要因が投資行動に大きく影響している。例えば、日本企業は北京に集中しているが、台湾企業は華南地区に集中する傾向がある。中国政府は台湾企業に対して外資としてではなく「自国籍待遇」を適用しており、そのような制度的な要因が立地要因に影響を与えているという。
以上の報告内容に対して、筆者は以下のようなコメントを行った。藤本教授の分析が示すように、党営企業の縮小、ハイテククラスターの発展に伴い経済機能の台北一極集中化は緩和されつつある。ここに「小さな政府」を目指す政策的な意図が表れているのかもしれない。しかし、その一方で台湾政府は新竹のほか、桃園、台湾中部、南部のサイエンスパークの発展に力を入れており、台北市の本社立地一極集中が急速に緩和される可能性がある。インフラ整備で台湾全国を短時間で移動できるようになり、ハイテククラスターの運営効率が高いということになれば、海外企業からの受注が今まで以上に増加することが容易に予想できるためだ。その意味で、政府の政策的な支援は台湾経済の発展に今後も強い方向性を与えていくのではないか。近年、経済地理学の世界では組織、技術、地理的空間相互のコーディネーションを一つの社会システムとして把握するアプローチが注目されているが、企業と地理的空間との相互関係を分析する上で、行政、すなわち国家が与える影響についても引き続き検討する必要があるのではないか。
以上を受けての質疑応答では、中小企業の本社機能は都市一極集中型になる傾向があり、企業の規模の大小を考慮して本社の立地構想を分析するべきではないか、民進党政権がオフィス立地パターンに影響を与えたのは党営企業の縮小という現象だけだったのか、民進党政権は地方分権化にどのような影響を与えたのか、地方分権化とは民進党政権が打ち出した明確なビジョンだったのか、外国人労働者の大量流入が本社機能の地方分散に影響を与えたのか、直轄市の増加が与える影響の是非等の様々な興味深い論点が提示された。
今回の報告は、経済地理学の領域から台湾企業の本社立地構造というテーマに切り込み、既存の台湾経済や台湾企業組織に新しい視点を与えただけでなく、アジア資本主義発展研究の新たな可能性にまで踏み込んだ斬新な分析結果となっている。今後、このような経済地理学、社会学、経済学、経営学、政治経済学といった社会科学の様々な理論的視角が台湾研究に取り込まれ、台湾経済や社会発展のより深く緻密な理解に大いに貢献することだろう。(田畠真弓記)