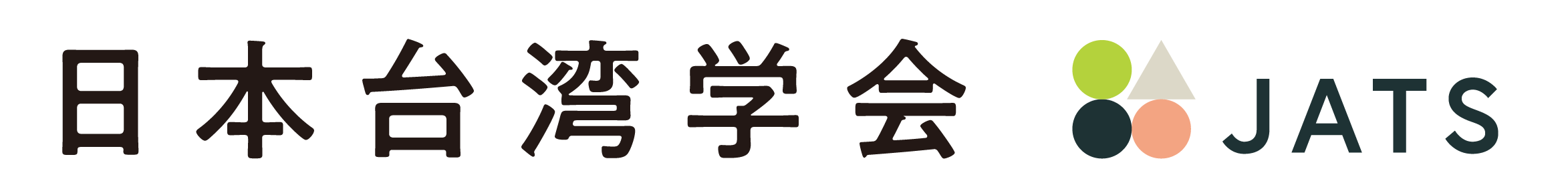日本台湾学会台北定例研究会
第53回
| 日時 | 2010年7月31日(土) 15:00開始 |
| 場所 | 淡江大学台北キャンパスD326室 (台北市金華街199巷5號) |
| 報告者 | 川上 桃子 氏(アジア経済研究所) |
| テーマ | 「『破壊的革新』の担い手としての台湾企業の興隆:IT機器産業の事例」 |
| コメンテーター | 田畠 真弓 氏(東華大学社会発展学系) |
| 使用言語 | 日本語 |
参加体験記
2010年7月31日午後3時から、淡江大学台北キャンパスD326室で日本台湾学会第53回台北定例研究会が開催された。報告者はアジア経済研究所の川上桃子氏、参加者は計15名であった。川上氏の報告「『破壊的革新』の担い手としての台湾企業の興隆:IT機器産業の事例」の概要は以下の通りである。
台湾の電子産業の発展は、従来、受託生産取引の拡大を通じて実現されてきた。ところがここ数年、台湾発のブランド企業が世界の電子産業の表舞台で頭角を現し、米・日企業の手ごわい競争相手に成長しつつある。これは、台湾の産業発展が新たな段階を迎えたことを示唆する重要な変化であると考えられる。
この新たな現象は、台湾企業による製品イノベーションの活発化の表れとして理解できる。本報告ではAbernathy&Clark[1985]によるイノベーションの枠組みと、Christensen[1997]の「破壊的革新」概念を手がかりに台湾の自社ブランド企業による革新を検討した。
具体的な事例として報告がとりあげたのは、ネットブック、液晶テレビ、簡易ナビゲーションデバイス(PND)である。アスーステックによるEeePCの開発は、典型的な「ニッチ創出型革新」であり、かつ「破壊的技術」の実践例であった。このイノベーションの重要な意義は、ノート型PCメーカーとしては周縁的な存在だったアスーステックが、産業秩序を完全に掌握していたインテルの行動に大きな影響を与えた点にある。またPNDと液晶テレビでは、ビジオやガーミンのPND部門のように、表向きは米国企業だが、実質的には台湾企業と呼んでもよいような「広義の」台湾系のブランド企業が台頭しつつある。
以上のような台湾発のブランド企業の興隆の背景としては、①これらの新興ブランド企業が、台湾の受託生産企業との緊密な協業とこれらの企業との交渉力を巧みに活用することで自らの競争力を高めてきたこと、②近年の電子産業では、製品の中核的な機能を一つのチップに統合化する動きが進んでおり、これが、製品開発をめぐる先発企業と後発企業の技術格差を縮める作用をしていること、が挙げられる。
台湾企業のなかからついに、製品市場の表舞台に登場し、日本や米国のブランド企業の手ごわい競争相手となる存在が出現しつつあることで、受託生産を通じた補完的・協業的な関係を基軸としてきた日台企業間の関係には変化が生じると考えられる。台湾の産業発展は新たな段階を迎えつつある。
報告に対するコメントは東華大学社会発展学系の田畠真弓氏がつとめた。発言の要旨は以下のとおりである。台湾のIT機器産業は、「そこそこ品質があって安い」製品を作ることによってニッチ市場を拡大させていったが、この点で川上氏がクリステンセンの理論をもちいて分析をおこなったのは的確であり、その意義を高く評価したい。クリステンセン自身も6月末に来台した際、台湾のアスーステックは破壊的革新の代表例だと発言している。では、そうした破壊的革新はいかなる条件のもとで出現、発展するものなのか。川上氏やクリステンセンは受託生産を重要な要素としてあげているが、あらゆる途上国において受託生産が破壊的技術を生み出すことになるのか。生産を受託する側は発注側のさまざまな要求に対応しなければならず、非常にきびしい環境におかれることになるが、途上国が先進国に対抗するにあたって破壊的技術がはたしうる役割はどの程度のものなのだろうか。
参加者からは、台湾企業のOLPC(One Laptop per Child)運動への取り組みや、今日さかんに喧伝されているMIT(Made in Taiwan)製品などと報告内容との関連、日本企業などが持続的技術から破壊的技術へとシフトできないことの背景、日本企業の台湾OEMメーカーに対する協力のあり方、台湾企業にとってのブランドを持つことの意味、などについて質問や発言があった。
複数のブランド企業から製造を受託される立場を利用し、ニッチ市場から主要市場へと打って出る力を獲得した台湾のIT企業のしたたかさ、巧妙な情報蓄積におおいに感心させられる報告であった。しかし、質疑応答である参加者から指摘があったとおり、今日までの「成功」は、台湾IT企業が今後、破壊的技術を利用した他勢力の追い上げにさらされることをも意味している。「アマチュア」の消費者のニーズをうまくすくいとることに成功し、それによって競争力をも高めてきた台湾IT企業は、あらたなステージにおいてみずからの立ち位置をどのように設定していくのだろうか。(冨田哲記)