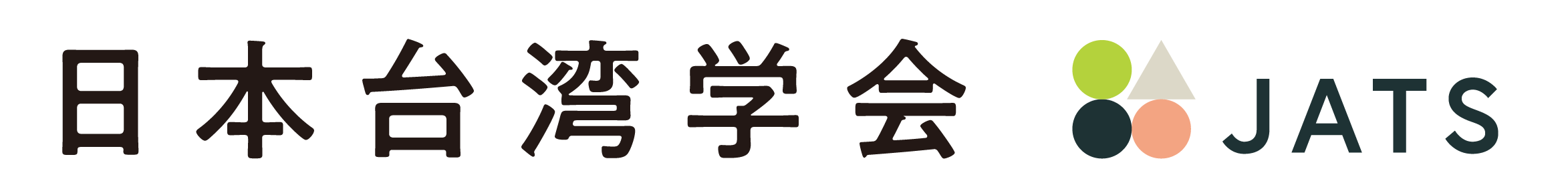日本台湾学会台北定例研究会
第68回
| 日時 | 2015年1月24日(土) 15:00開始 |
| 場所 | 国立台北教育大学行政大楼A605室 |
| 報告者 | 林 琪禎 氏(和春技術學院應用外語系/文藻外語大学日本語文系(非常勤) |
| コメンテーター | 藤井 康子 氏(国立清華大学外国語文学系/天主教輔仁大学日本語文学系) |
| テーマ | 「日本統治期国民学校制度の問題性」 |
| 使用言語 | 北京語、日本語 |
参加体験記
2015年1月28日、第68回台北定例会が開催された。今回の発表者は林琪禎氏(和春技術学院応用外国語学科助理教授)である。参加者は11名だった。
報告者は、日本の教育制度史上で実施期間がわずか4年間だった、戦時体制に応じたとも言える学制を取り上げ、その植民地おける実態を中心に考察した。
国民学校制度は、植民地台湾と朝鮮でも同時に推し進められたものであるが、植民地の教育で重要なのは、中身はともかく、元来植民地では「内地人」(日本人)と「現地人」(台湾人、朝鮮人)に別系統で教育を行ってきたものが、この時点で一本化されたということである。台湾を例とすれば、従来は日本人子弟は「小学校」、台湾人子弟は「公学校」に通っていたが、1941年に「国民学校」に統一された。このように植民地と本土が一斉に「国民学校」制度を実施することは、「内外地一元化」という施策の一環でもある。教育制度が「統合」され、内地では国民の「錬成」を掲げる一方、植民地の台湾と朝鮮では「皇民化」のさらなる強化が追求された。もっとも、政府側は「皆立派な日本国民に」という「建前」を掲げたものの、従来と比べてどれほど「統合」したのか、あるいは「地域差」を温存したまま、植民地主義的な教育が続行したのかをあきらかにしたいというのが本報告の趣旨だった。
従来の植民地教育の研究は、明と暗という二元対立の傾向が強い。前者では「植民地近代性」において教育の貢献を強調し、「差別」は過小評価されてきた。それに対し、後者は教育や社会制度に存在した「差別」を批判し、マイナス的な評価を強化してきた。ただ、両者とも盲点が存在する。植民地問題を議論する際、どのように「称揚」と「批判」の対立から脱却し、全面的な評価を下すのかが、大きな課題の一つである。一地域に留まる研究ではその全貌を掴めず、日本内地や他の植民地と比較する必要がある。
日本における国民学校についての先行研究の蓄積は豊かなものの、植民地まで視野を広げたものは少ない。植民地教育史の研究も豊富な成果をあげてきたが、期間の短い「国民学校」時期を中心とした研究はほとんどなかった。なので、内地と植民地の「国民学校」時期の教育実態に着目し、全体的に論じることは、教育史研究を更に補完することにもなる。
国民学校制度の実施により、日本内地では義務教育期間の延長もおこなわれることになっていた。しかし、義務教育制度は植民地には一斉に実施されなかった。台湾では1943年にようやく初等教育が義務化され、朝鮮では1946年に義務教育を実施する予定だったが(敗戦のため未実施)、この意味で、「内地」と「植民地」の差が依然として存在していたことは否めない。また、義務教育が国家意識やナショナリズムを培う重要な方法の一つであるという視点から見れば、戦時期に義務教育が講じられたのは、国家イデオロギーの強化を大きな狙いとしていたからだと思われる。
日本統治末期の台湾総督府台北師範学校を前身とする台北教育大学で教育問題が論じられるのは意味深いものだった。特に同大学の何義麟先生からは、日本では1947年から「国民学校」の名称が「小学校」に戻ったものの、民間では「国民学校1期生会」という団体で、国民学校が存在した歴史を語り続けているという指摘、また、現在の台湾で「国民小学」、「国民中学」などの名称が残っているのは、日本統治期の国民学校制度のなごりなのではないかなどのコメントがあった。(王敬翔記)