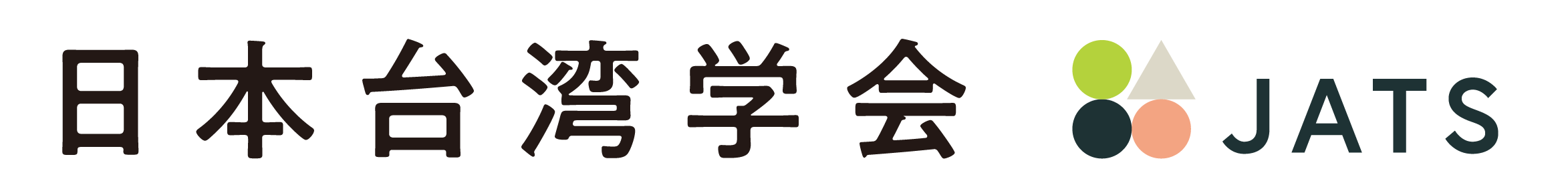最終更新:2011年2月1日
|
岸川会員の台北便り2003.8-2004.3 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第1回 SARS後の台北より(2003年8月1日) 皆様はじめまして。今月から台北便りを担当することになりました岸川と申します。6月より中央研究院社会学研究所の訪問学人として台北に滞在しています。 専門は比較政治学で民主化後の台湾で展開される政党政治や市民社会の動きに関心を持っています。ただ台湾研究は始めてまだ数年で、長期滞在も初めてですか ら、政治ウォッチャーとしては修行段階です。したがってこの滞在は、政治学者としての専門的な研究という以上に、台湾の人々の生活に広く接する機会にした いと考えています。そのようなわけで、先月まで台北便りを書かれた佐藤先生のような内容の濃いものは望むべくもなく、台湾を熟知されている会員の方々に とってはあまり目新しくもない素朴な体験談や、経験の浅い者にありがちな的外れな感想も書いてしまうかと思いますが、どうぞお許しください。 さて、今回は7年に一度の大学の研究休暇を利用しての待ちに待った台湾行きでしたが、SARS危機のなか、マスクや体温計や消毒薬を持って人影もまばらな中 正国際機場に降り立つという、あまり順調とは言えないスタートとなりました。もっとも私が来た頃には感染者数は頭打ちとなり、定時の政府発表や対処法のマ ニュアル化といった「抗SARS」体制も整ってきていました。逐一報道される院内感染の状況、建物に入るたびに受ける体温測定、捷運など公共交通機関でのマスク着用は危機を実感させるに十分でしたが、台北の人々はすでに慣れた感じの冷静な対応で、私もすぐに日常生活の一部となりました。やがて感染は収束 し、台北は賑やかで活気のある姿をほぼ回復しています。いまでも犠牲者を悼む報道はありますし、WHOの差別的対応や中国への不信感の強まりを背景に危機 意識を喚起する議論は聞かれますが、全体としては急速に過去の出来事になりつつあるようにみえます。この危機の意味をいまいちど全民的に再検討しないで良 いのだろうか、と思うことも少なくありません。 いまでは台湾のメディアは花蓮県長補選、公投、総統選挙をめぐる攻防といった政治の話題か ら、街の奇人変人、日本のAV女優の来台まで、堅いものも柔らかいものも、根拠のしっかりしたものも怪しいものも、多彩な内容をすべて「同列に」報道する いつもの姿を取り戻しています。正論を言うと、これは報道の質に関わる由々しき問題なのかもしれませんが、この雑多で混沌としたあり方には面白さも感じま す。報道メディアに限らず、日常の使用言語しかり、食事しかり、流行しかり、生活のあらゆる面において異質なものが交じり合う雑然とした状況をみると、こ れこそが台湾なのだと感じます。台湾社会がもともと持っていた多元性が解き放たれ、そこにグローバリゼーションのもたらす外来の要素も加わった結果という 意味で今日の台湾というべきかもしれません。いずれにせよ「異質な要素を明示的に分類し系統付けて整理する」という発想自体が台湾社会には薄いように思え ます(否定的な意味ではありません)。だからといってそれは必ずしも無制限で無秩序な多元性というわけでもなく、ごく自然に日常的になされている国語と台湾語(閩南語)の使い分けのパターンに見られるように、一定の規則性を見出せるのも確かです。そうした多様な要素が具体的にどのように使い分けられ、共存 しているのかということには非常に興味があります。 そこで今日は、雑多さの典型とも言えるテレビについて書きます。民主化後の新たな環境 において無線局が定着しないまま100近くものチャンネルを持つケーブルテレビ時代へと移行した台湾のテレビには、インターネット上をさまよう時のような とりとめのなさを感じます。ひと巡りするだけでも疲れる数の多さですが、SARSの影響もあり家でテレビと向かい合っている時間が長かったので、どこで何 をやっているかはだいたい把握できました。ケーブルテレビの普及と多チャンネル化自体は台湾に限ることではありません。しかし使用言語、番組の種類・国 籍・質の多様性において、そしてこれらが優劣の区別なく同列に並べられている点において、台湾のテレビは独特であるように思えます。しかしその一方で、こ と政治に関しては、馬英九台北市長に対する格別に好意的な扱いなど、やはり「藍」に寄っていると感じることが少なくありません。そしてもうひとつ、近年に おける台湾語の占める割合の増加は印象的です。 台湾語ドラマの種類は再放送も含めるとかなりの数に上りますし、台湾各地の風俗や文化を紹 介する番組も台湾語中心のものが少なくありません。これらはまだ字幕がついているぶん国語のみの話者にも問題ないとしても、「全民開講」(TVBS)を始 めとする討論番組ではしばしば字幕無しで国語と台湾語が交じり合います。視覚メディアに関する限り台湾語が理解できないと楽しめる範囲が限られてくるわけ です。メディアにおける台湾語の地位の変化については、『日本台湾学会報』第五号の菅野敦志氏の論文「中華文化復興運動と「方言」問題 (1966~1976)―マスメディアの「方言番組制限」に至る過程を中心として―」をたいへん興味深く読みました。「方言」の駆逐を前提としながら、台 湾語のわずか一割の枠をめぐって攻防が繰り広げられた当時のディスコースには隔世の感を覚えるとともに、その法的根拠としての広播電視法が改定されたのが やっと93年であった事実を思うと、民主化に伴う変化がいかに劇的だったかを再認識させられます。私が初めて台湾を訪れたのは95年の春でしたから、私が 個人として体験した変化も、もっぱら改正後の短い期間のことであるにすぎません。 台湾語の番組のなかにはきわめて話題性の高いものもあり、このところは「霹靂火」(三立台湾台)というドラマがちょっとした社会現象になっていました。「霹靂火」は、善と悪の企業グループの経営者一族間の熾 烈な争いを描いた、日本の昼のドラマをさらに誇張したような、台湾語ドラマにありがちなストーリーです。しかし拉致や殺人などの暴力シーンがひときわ多 く、登場人物が次々と亡くなっていく極端な展開が特徴で、とくに悪役・劉文聰を演じた秦楊のテンションの高い演技が受けて、普段は泥臭い台湾語ドラマを見 ない学生やOLまで引き込んだと言われます。劉文聰のモノマネも盛んで、パロディー討論番組の「全民乱講」(中天資訊台)では有名政治家の真似に混じっ て、劉文衝という名の人物がほぼレギュラーで登場しています(実は私はこの番組を通じて「霹靂火」の存在を知りました)。インターネット上では劇中人物や ストーリーを評価するスレッドが立てられ、新聞や雑誌でもこのドラマに関する記事やコラムがお馴染みになりました。面白半分に取り上げたものから、低俗で 教育上問題が多いという真面目な批判、内容はともかくドラマが台湾の土着文化を広める手段となり得る可能性を示したという評価まで取り上げ方は様々です。 先日は、林森北路で打工をする大陸妹の摘発に「霹靂火」が役立ったという話も伝えられました。報道によると、不法滞在者を摘発する手段として通常警察は国家 を歌わせたりするのですが、これはすでに相手側に知られているので、新たな手として劉文聰のお馴染みの台詞「我若不爽、我就想要報仇」を知っているか尋ね たところまったく理解できず、外国人と分かったとのことです。ドラマの放映は先日終了しましたが、ブームは当分続く気配です。霹靂火の写真・台詞集が発売 され、劉文聰の台詞が携帯電話の応答メッセージに使われ、劉文聰役の奏楊が音声を担当したコンピューター・ゲームがヒットしています。そして花蓮県長補選 では、游盈隆、謝深山、呉國棟の三陣営がともに造勢活動に秦楊ら霹靂火の主役を呼びたがっていると数日前の新聞が報じていました。秦楊本人に特定の政治的 立場や支持政党はなく、要請があればどの候補の造勢活動にも参加可能と経紀人は言っていますが、呉国棟候補と一緒にステージに上っているところを昨日テレ ビのニュースで見ました。政治家がすぐにこの種のブームに乗って俳優の取り合いをするあたり、やはり台湾的なのでしょうか。 SARSが去ったことで、いまではテレビを見る時間もずいぶん減り、夏休みで賑やかになった台北の町を歩きまわることが多くなりました。蒸し風呂のような毎日ですが、こういう気候は嫌いではありません。むしろ気になるのは、涼しくなる秋以降SARSがまた戻ってくるとの予測があることです。そうならないように祈るばかりです。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第2回 台湾国語と台湾語と(2003年9月8日) 初回の台北便りから既にひと月余りが経ちました。中秋節が近づくにつれ月餅や文旦が出回るようになり、私の住む公寓でも中秋節の懇親会のお知らせが来ていました。まだ変わらぬ暑さとはいえ、店に並ぶ果物が徐々に変わっていくところが季節の変わり目を感じさせます。中央研究院を訪れた初日には端午節の粽子を御馳走になりましたが、それから七夕節、中元節、そして中秋節と、台湾が農暦で動いていることを実感させられます。とくにこの一ヶ月は街角で金紙を燃やす火が暑い夏をいっそう暑くしていて、公寓でも七月十五の普渡が盛大に執り行われました。跳梁跋扈する鬼を宥める金紙には色々な種類がありますが、スーパーの金紙の安売りの広告に、七月初一の接好兄弟から始まる一ヶ月間の祭拝対象と使用すべき金紙のリストが載っていて勉強になりました。夏の中央研究院は、事務所や図書館こそ開いているものの、海外に出ている研究者も多く、研討会を初めとする学術的イベントもその多くが休止状態です。こちらの話題はまたの機会にまわすことにしましょう。 昨年より中国語での台北定例研究会が時々行われているとのこと。こうした研究会は台湾人研究者との交流促進の場として、また日本人研究者が現地語の討論に慣れる機会を提供する場として有意義な役割を担うことができると思います。私がこれまで主に関わってきた中南米関係の学会の場合は、現地での定例研究会自体が困難でしたから、こうした試みが可能な状況が羨ましくも感じられます。とくに若手の研究者にはこの種の研究会はあまり失敗を恐れずに発言できる良い機会ではないでしょうか。かく言う私はというと、中国語の水準を十分に高める暇もないまま在外研究の年が来たというのが実情で、資料を読むのは大丈夫なのですが、会話を含む運用能力となると一気に水準が落ちます。このギャップを埋め中国語の討論にも積極的に参加できるようになることも滞在目標の一つで、その点は学生の方々と変わりません。今日はそのような入門者の立場から、言葉の習得の問題を取り上げてみます。 初めての「中国語環境」下の生活も三ヶ月が過ぎ、コミュニケーションはいくぶん楽になってきました。自分がこれまで使ってきたスペイン語など欧米の言語と比べ、中国語はとくに聞き取れるようになるまでの壁が厚いように思えますが、それが言語の構造の違いによるものなのか、言語習得のシステムの充実度の差によるものなのか、それとも私自身の年齢の問題なのかはよく分かりません。それはともかくとして、もう一つ強く感じるのは、いわゆる北京語との違いが何かと支障を来たす点です。北京話は表記法や発音や文法に関して標準化が進んでいるわけですが、台湾国語の場合、基本的文法や語法を共有しているとはいえ、標準化のされ方や度合いが異なっているうえに、異質な要素を色々含んでいます。日本人のほとんどは北京語で中国語を学びますから、何らかの形でこれらを克服しなければなりません。中国文化圏に関する素養を十分に身につけた上で台湾を研究する場合にはさしたる問題ではなく、台湾に来て慣れれば良い程度のことなのかもしれませんが、私のように直接現代の台湾から研究を始める場合はそれなりに苦労しますし、また言語の標準化や教育体制に関する政治的な要素が関わっているとの印象も持ちます。 違いを列挙すると、繁体字、注音符号、固有名詞の英文表記、発音、語彙などということになります。第一に漢字の違い。繁体字と簡体字の対応関係に慣れれば読むのには問題はなくなりますが、初めは辞書を引くだけでも時間がかかりますし、実際に文字を書くとなると慣れるのはそれなりに大変です。第二に注音符号。北京語のピンインに慣れた後での切り替えはなかなかやっかいです。パソコンの注音入力は普及していて、文献の検索などで使うコンピュータのキーボードも多くの場合注音入力ですから、単に読み方だけでなく打ち方も慣れなければなりません。第三に固有名詞の英文表記。一定の規則性は見出せますが、究極的には人名は個々に覚える必要があり、地名の表記には複数の方式が使われていて全体として一貫性がありません。北京語の統一された表記システムに慣れていると、統一されていないこと自体にも戸惑います。第四に発音。舌尖後音(sh、ch、zh)が、舌尖前音(s、c、z)に近くなることを知ってはいても、やはりはじめは聞き取りにくい。日本人にとって発音が楽な反面、聞き違いも多くなります。その他にも微妙な音の違いがあり、実践のなかで慣れていくしかありません。第五に語彙。台湾国語には台湾語、原住民語、日本語といった複数の起源の言葉が数多く入り込んでいるため、食材の名称から社会科学の用語まで、いったん覚えた北京語の単語や表現を修正していく作業が日常的に必要になります。 これらひとつひとつは大きなハードルではないにせよ、全部をクリアするとなるとそれなりの手間と時間を要します。それに、これらのことを手際よくまとめた教本の類を見たことがありません。そのためもし日本で台湾国語の語彙や文字や音に慣れ、台湾社会の実情に即した内容で学ぶとなると、台湾で出ている日本語教材を逆に利用したり、字幕付きの台湾映画やテレビ番組のビデオやDVDを教材として使う、といった工夫が必要になります。近年技術の進歩がある程度これらの負担を軽減してくれているのは確かです。文章を書くには、日本で市販されている中国語ソフトを使えばピンイン入力で繁体字が打てますし、簡体字と繁体字の転換もできます(しかし繁体字は辞書機能や翻訳機能が使えないなどまだ対応は不十分です)。分からない繁体字は、手書き入力機能が即座に解決してくれます。それが可能な電子辞書は台湾で何種類か売り出されていて、私は『快譯通』というのを使っています(ただ、やたらと多くの機能があるわりには使い出が悪く、漢字を調べる以外にはあまり使えません)。ちなみに日本でつい最近出たCASIO『EX-word』の中文版は使いやすいのですが、もちろん北京語で、先日台湾人の友人に見せていて「台湾」を引いたところ、「中国の省の一つ」との説明が出てきて気まずい思いをしました。この機種の台湾国語版、しかも手書き入力可能なのが出たら申し分ないのですが…。 しかしこれらの対策は結局のところ、場当たり的な試行錯誤の域を出ません。日本人にとって根本的な問題は、台湾国語を習得するシステムが未整備だということです。台湾国語の標準化は当然台湾で議論されているわけですし、単に経済合理性や使いやすさだけでは決められない敏感な面を含む台湾人自身の問題です。しかし学習システムの整備の問題は日本人の側の問題です。いま日本の書店の外国語コーナーには、少数言語と言えるものも含め実に多くの言葉の教本が並んでいます。私が学生の頃と比べて、中国語関係の教材は格段に充実しています。しかし日本の言語教育界は「統派」か、と思いたくなるほど台湾国語の存在感は薄いままです。二千三百万の人が使い、日本との関わりが非常に深い国の語学教材がもっと整備されても良いのではないでしょうか。 さて、台湾のもうひとつの言語すなわち台湾語(台湾閩南語)の場合はどうでしょう。研究への必要性という点では、政治に関するかぎり公文書、学術論文、報道などの文章は基本的に国語です。演説や討論に台湾語が使用される場合の聞き取りの問題はあるにせよ、少なくとも現段階で私にとって差し迫った必要性があるわけではありません。中南部ならともかく、台北にいる限り台湾語ができなくとも肩身の狭い思いをするわけでもありません。ただそれでも、一歩外に出ると台北の街角のあちこちに台湾語の世界があります。国語で生活しているつもりでも、「歹勢」などの基本表現が日常的に使用され、新聞の見出しには「打?」や「運將」といった言葉が並びます。私の住んでいる捷運雙連駅周辺はかなり台湾語濃度の高い地域でもあり、自助餐や屋台で台湾語で話しかけられることがありますし、こちらから話すとたいがいは優しく応じてくれます。台湾語を話したいと思うのはごく自然な感情と言うべきかもしれません。 私は数年前から少しずつ勉強していますが、やはり台湾語も日本人が学ぶとなると、むずかしい問題に直面します。第一に日本では台湾語の教材が非常に少ない。そんななかで樋口靖著『台湾語会話』(東方書店、1992年)はコンパクトながら体系的な構成と情報の豊富さにおいて、そして音声教材(テープ、現在はCD)が付いている点で画期的な意味を持っていたと思います。運用能力を高める形での言語習得には耳の訓練を伴った学習が不可欠な要素ですが、とくに台湾語は基本的に話し言葉であり、またその転調は頭だけで覚えるにはあまりに複雑で、ここを乗り越えるかが習得の重要なポイントですから、音声付きの充実した教材が市販されたことの意義は大きいと言えます。第二に台湾語には、表記法の統一や文法の整備が進んでいない現実があります。1990年代に本土化の呼び声とともに、多数の台湾語教材や関連図書が出回るようになりました。しかし個々の著者が自らの主張する表記法や文法を用いるため(すべて漢字で表記するか、漢字とローマ字を組み合わせるか、すべてローマ字にするか…)、それぞれに著者の工夫が見られて味わいがある反面、どの方法を用いて学ぶかは結局読者の判断に委ねられます。第三に外国人向けの教材がほとんどないだけでなく、大半の教材が子供に郷土文化を学ばせる目的のもとに編集されています。台湾語を母語とする人が七割以上で台湾語を解する人が九割と言われる状況で作られる教材ですから、ある意味当然のことです。 このような事情のため、日本人が台湾語を学ぶとすると、一般的には日本の教材から始めて台湾の教材へとつないでいき、必ずしも一貫しない表記や文法説明を自分なりに整理しながら習得していくというやり方になるかと思います。台湾で出ている教材は玉石混交ですから、適当な教材を選び自分に合った使い方を模索することも必要になります。私は『輕鬆講台語』(開拓出版、1994年)をはじめとする方南強編著のシリーズが、内容豊富でテープも付いているので気に入っています。王華南著『實用台語詞彙』(臺原出版社、1998年)など補助教材として役立つ語彙集の類はかなりあります。語学と語学教材集めは私の趣味でもありますので、台湾語に限らず複数の言語が、自由化された多言語状況のなかで自己主張を始めている台湾の状況には興味が尽きません。関連図書が山と積まれる台大近くの「台湾e店」はいつまでいても飽きません。 ところで台湾語の教材や資料の多くには、本土化への思いや「独派」の主張が込められています。そして公の場で台湾語を使う場合、それ自体がしばしば政治的メッセージを伴います。一昨日、李登輝氏の呼びかける「正名運動」の遊行を見に行きましたが、その演説といい周りで飛び交う台湾各地の人々の言葉といい、圧倒的な台湾語の世界を経験できました。ただ、台湾語の地位の向上と言語多元主義のロジックとの間には時として緊張やズレが生じます。一方で台北には、三言語(プラス英語)で流れる捷運やバスの駅名アナウンスのように、実用性というよりは言語多元主義を確認することが目的とも思える社会装置があります。七月に「客家電視」が開局した時に陳総統や主要政党指導者が片言の客家語で挨拶していた姿にも、票集めの思惑があるにせよ、多元主義社会の作法とも言える姿がありました。しかし台湾語の地位の向上そして「閩南語=台湾語」という用語法自体に、一言語の地位を特別に高める意思と力がはたらくのも確かです。昨年、私の授業を取っていた台湾人留学生が尋ねてきて族群関係の話になったのですが、彼女は客家なので、民主化で台湾語の地位が上がるのは良いが、それが公用語のような地位を得ると自分には必要な言語が増えて大変だ、複雑な気持ちだと話していたのを思い出します。多元社会の現実にはなかなか難しいものがあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第3回 「全民参加」の民主主義?(2003年10月13日) 中秋節を過ぎた頃から台北も涼しくなり、最高気温が30度に達しない日も多くなってきました。一方、総統大選まで半年を切って政治の方はこれから熱くなっていく気配です。民意調査で連宋陣営に水をあけられている陳水扁陣営が差を縮めることができるか、中間選民はどういう動きを見せるかといった話題がマスメディアでは限りなく議論されています。最近は公民投票や新憲法制定の表明と、陳陣営が攻勢をかけていて、当然これから双方がいろいろ手を打ってくるのでしょう。しかしこうした政党の側の思惑はともかく、いま台湾では社会の側から直接参加を要求する濃厚な空気が漂っています。国家アイデンティティーや核エネルギーといった全国民的な課題から、国営企業、教育、農業など部門ごとの利益、さらには地元のゴミ処理場や道路建設といったきわめてローカルな問題まで、街頭に出て主張し要求する光景が日常のものとなっています。このなかには反核運動のように歴史の長いものもありますが、あらゆる分野で噴出するようになったのは去年あたりからだと指摘されています。 この夏の目立った動きとしては、例えば林義雄氏率いる「核四公投千里苦行」や李登輝氏らの「正名運動」がありました。どちらもかつて大政党の党首を務めた指導者が街頭の運動を率いるというものですが、スタイルは対照的です。陳水扁政権が第四原発を存続させたことで、党から距離を置くようになっていた林義雄前民進党主席の主導する反核運動は、炎天下を黙々と行進する静かなもので、6月に第三波の千里苦行を終えたあと、7月4日の総統府前の集会で一つの区切りを迎えました。その時々の規模は必ずしも大きくないものの、活動は十年前から続けられていて、大火を自らの羽根で消そうとする鸚哥が天を感動させて火が静まるという仏典の故事にならって行動する林義雄氏が、総統府前で静かに座り込む姿には、強い信念に裏付けられた独特の迫力があります。 この運動の主眼は反核とともに、民主主義の深化のための公民投票(国民投票)の実現にあるわけですが、公投に向けた動きは、陳総統が来年の実施を明言し、行政院で公民投票委員会が発足、民進党が結党17周年記念式典で主要目標として掲げるなど、この夏の一連の動きの中で前進しつつあり、各種民意調査の結果も概ね公投実施を支持しています。もちろん議題は核四に限らず国会議席削減やWTO加盟などがあり、いまは実施の枠組みをどう整えるかが、公投法という形で与野党間で審議されています。最大限に促進したい泛緑と、できるだけ制限(主権問題や諮詢性公投を禁止)したい泛藍という構図ですが、議論の主軸は民意の促進か体制の安定かというきわめて根本的な政治哲学論争です。どのような形になるにせよ、政治家に濫用される悪しき民粋主義に陥らないためにも、またいまだ国民投票を本格的に実施する国のないアジアにあって台湾の経験がパイオニア的な意義を持ち得るという意味でも、しっかりとした制度枠組みの構築が期待されます。 さてもうひとつの大きな動きとして、昨年黄昭堂氏らによって始められ李登輝前総統が総召集人を務める「511正名運動」の10万人規模の大遊行が、9月6日に行われました(もっとも数字の方は5万人から15万人までと報道によってずいぶん違います)。台聯、民進党、李友会など独派諸団体の主導する遊行が、七つの場所から出発して凱達格蘭大道で合流したときの、紫と緑の交じり合う光景は壮観でした。二二八公園、総統府前、中正紀念堂あたりを歩き回った印象としては、各地からバスで乗り付けてきた人々が多数を占めていて、年齢層は比較的高かったように思えます。また各団体の小さな演説会があちこちで行われていて、思い思いのやり方で参加している感じでした。動員された集会にありがちな、配布されたグッズが捨ててあるようなことはほとんどなく、旗や鉢巻きを皆大切に持っていたのは印象的で、おかげでグッズ集めはできませんでした。凱達格蘭大道の反対側ではこの日、特大サイズの中華民国国旗を掲げた国民党本部のなかで三中全会が開催されていて、そこも正名運動の参加者が取り囲んで気勢をあげていました。 大遊行のクライマックスとなった李登輝氏の演説は、炎天下にもかかわらず、80歳という高齢でしかも十日ほど前に心臓の手術をしたばかりとは思えない力強さがあり、台湾語で語られる「中華民国無存在」というフレーズが非常に鮮明に耳に残りました。後に陳総統が2006年の新憲法制定を目指すと宣言したことで、それを支援する李登輝氏の発言もますます活発になっていて、公職を離れて吹っ切れた心持ちもあるのでしょうか、ある意味いま最も元気のある政治家です。なお翌日に対抗して行われた「中華民国擁護」「反台独」の遊行には数千人が参加と報道されました。もっとも運動そのものが盛大だった正名運動も、遊行前後のTVBSの民意調査をみるかぎり、国号として中華民国を支持する意見が五割台、台湾国ないし台湾共和国は約三割とあまり変化は見られず(むしろ中華民国の方が微増)、この結果が正しければ民意全体のバランスを変えるものではなかったことになります。 ところで、また別の流れとして自治体レベルの抗議や意志表明もいま盛んで、それを公民投票(住民投票)によって確認する動きが高まっています。こちらの方は核四建設に対する台北県貢寮郷の公投をはじめ過去にいくつか実施されているわけですが、このところ数が増え内容が多様化しつつあります。最近注目を浴びたのは、高速道路のインターチェンジの一般開放を要求する台北県坪林郷の公投(9月13日)と、ゴミ焼却場建設に反対する南投県集集鎮での公投(10月4 日)で、どちらも地元民の圧倒的意志が確認されました。成立はしませんでしたが、雲林県林内郷ではゴミ焼却炉建設に関連して台湾地方自治史上初となるリコール投票も実施されました(9月20日)。いままさに公投を前面に掲げる民進党としては、こうした自治体レベルの公投も尊重する姿勢を示さざるをえないものの、政権党として推し進める政策が地元民から拒否されるという難しい局面にも直面するわけで、歯切れの悪さは否めません。 そんななか、馬英九台北市長が行政院会で最近の公投熱を文革に例えたとして緑営側の激しい非難を浴びました。馬市長は大陸台商の言葉を引用したのが捻じ曲げて伝えられたと反論していますが、それはともかく、欧米でも日本でも直接民主主義の批判者が挙げるお決まりの例はファシズムですから、文革が来るあたりはやはり中国語圏だと妙に感心しました。また先日、専門家の意見が住民より優先されないのなら、適切な環境政策は実施できないとして、郝龍斌環境衛生署長(新党)が辞任したことが論議を呼びました。このように公投の動きは、泛緑・泛藍の価値観の違いを炙り出し先鋭化させる作用も及ぼしています。なお地方自治体としてはいま台北市議会が先頭を切って公投の立法化を進めています。 しかし確かに自治体レベルの公投にはいろいろ問題点が指摘されています。ゴミ処理場のように不可欠な施設を拒否したら別の場所に行くだけで、主張されるのは「公」というよりは「私」益に近くなりますし、同じ問題でも郷鎮、県市、国のどのレベルで投票を行うかで異なる「民意」が出てくることがあり得るわけで、実際坪林公投の問題も全国レベルの民意調査では少数の支持しか得られていません。しかし政治家や専門家がどう言おうと、連鎖反応は止まりません。実施の動きがある自治体を新聞報道などから拾うだけでも、ゴミ焼却場建設に反対する苗栗県竹南鎮、同じく高雄市小港区、変電所建設に反対する宜蘭県羅東鎮、インターチェンジの増設を求める苗栗県西湖郷、防音壁設置を要求する南投県名間郷仁和村、火葬場建設に反対する雲林県斗六市八徳里、観光客を遠ざけるとして清潔管理費徴収の廃止を求める台北県烏来郷、墾丁国家公園の名称変更を求める屏東県恒春鎮、かつての美名・霧社を再び郷名に採用しようと提案する南投県仁愛郷、里名が卑俗であるとして変更を求める桃園県中壢市芝芭里、とリストは限りなく続きます。 市民社会が姿を現わし自己主張を始めるのは民主化の過程で見られる典型的な現象ですが、民主化研究でよく指摘されるのは、ひとたび自由民主体制への移行(=自由選挙の実施)が達成されると、市民社会が共通の目標を失って細分化し、やがては政治への関心も薄らいで私的な生活領域に閉じこもるというパターンです。一般に民主化が国民の期待を高めるのに対して、民主化後の政府が経験不足もあって期待どおりの成果を挙げられず、国民が失望するという状況に新生民主主義国は直面します。確かに台湾でも政府の能力に対する不満が蓄積しています。しかし体制移行を達成してすでに7 年を経過した今日、国民的課題、地元の問題、それに今回は触れませんでしたが農民、労働、教師など部門ごとの問題と確かに要求は多元化しているものの、あらゆるところで人々が政治に直接はたらきかける点で、いまの台湾の状況は、政治への無関心が蔓延したり逆に武力衝突にいたったりする他の多くの新生民主国家と異なっています。 なぜ人々は街頭に出て要求するのでしょうか。必ず指摘されるのが民進党の問題です。民進党は党外の時代から街頭での政治を担ってきたけれども、政権についてから社会の側の要求に応えなくなってしまった。様々な社会部門が要求を表出する政治のチャンネルを十分に確立できていない。任期半ばになっても変わらない。再び街頭に出て主張するしかなくなった、というわけです。確かにそうですが、しかし政治の側が応えていないというだけなら他の民主化後の国々も同じで、それらと比べてなぜ台湾社会がこれほど身軽に活動し主張するのかは依然説明できません。やはり別のところ、例えば社会そのものの持つ「台湾らしいなにか」があるのではとの思いにいたります。テレビやラジオで盛んなコールインや、街角の台湾人の議論好きや声の大きさが余計にそう思わせている部分もあるかもしれませんが、いずれにせよ、あらゆる人々がもの申す「全民参加」とでもいうべきこの濃厚な空気はどこから来るのでしょうか。 それが歴史や文化となると浅学の身にはまだ手に負えませんが、ひとつ台湾に来て実感したことがあります。それは国の体感規模とでも言うべきものです。2300万は決して少ない人口ではありませんが、人々は小さい国土に密集して住んでいて、全国を鉄道、バス、飛行機が過剰なほど行き来しています。そこで生活や環境を語るとき、美しくて壊れやすい小さな国土というイメージが喚起されます。なにか行動を起こす気になれば、国のどこからでも比較的容易に総統府や中正紀念堂に到達可能です。国の大事も街角の些細な争いごとも一緒にして伝えるマスメディアも、国民的課題と地元の問題をいちどきに身近に感じさせるのに一役買っているかもしれません。こうした要因が背景にあることで、少なくとも直接民主制の雰囲気ができやすくなっているように思えます。隣にあるとてつもなく大きい国が、なおさら台湾を小さく感じさせます。 もっともこの全民参加の風潮も、ことによると総統選が終わると一気に沈静化してしまうのかもしれません。しかしいまは、中国語圏で成立した史上初のデモクラシーは、直接民主制の要素を強く持った独特の形を作りつつあるのではないか、そんな可能性を思い描きながら台湾社会をみていきたいと考えています。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第4回 非常報導(2003年12月3日) しばらく一時帰国している間に、台北はすっかり涼しくなっていました。もちろん日本の比ではありませんが、体感温度の差なのでしょうか、台湾の人にとっては十分寒いらしく、厚手のコートにマフラーとすいぶん重装備の人を見かけます。日本人でも何年か住むと感じ方が似てくるそうですが、私にはまだ「涼しく」感じられます。この間に、総統選挙をめぐる状況に動きが見られました。民意調査で連宋陣営に水を空けられていた陳水扁陣営の支持率が10月後半に上昇し、総統のイメージを高めたと言われる米国・パナマ訪問を終える頃には、『中国時報』(11月5日)が陳呂35%、連宋34%、『聯合報』(11月11日)が陳呂38%、連宋42%と、両者の差がほとんどなくなりました。その後は再び連宋が優勢と出ていますが、数字は今後も上下することでしょう。両陣営が競り合うなかで、造勢活動はもちろん、台湾国民党への改名提案、十大建設計画の発表、国親版公投法の国会通過と色々なことが起こります。おかげでテレビの政治討論番組の視聴率はどれも上昇傾向にあるそうです。 しかしメディアを最も賑わせた出来事は、「非常報導」(台湾革命媒体工作室製作)と題されたシリーズ物のVCDをめぐる一連の騒動だったと言って良いでしょう。事の始まりは11月4日から5日にかけて、同VCDの中で攻撃の槍玉に挙げられた親民党の宋楚瑜党首と邱毅議員が怒りの会見を行い、邱議員と親民党が製作関係者と見做す多数の団体・個人を告訴したことでした。一方、台北市新聞処は認可手続きや表示に違法性ありとして、同VCDの製造元や販売所を捜索し一時没収する措置をとりました。VCDを配布していた「台湾e店」も取締り対象となり、報道陣が押し寄せるシーンがテレビに映し出されました。このあとさらに邱議員は「幕後黒手」として台視董事の江霞、大学教授でトーク番組を持つ謝志偉、作家の呉錦發、イラストレーターの漁夫を名指しします。こうして数多くの人を巻き込みつつ、憶測が飛び交うなかで騒ぎは拡大していきます。私はその最中に台湾を離れたため現地体験としては空白の期間があるのですが、まさに選挙戦が激化する「何か起こりそうな」雰囲気の中で発生し、ひと月も続いているこの出来事について、ここまでの経緯をまとめてみたいと思います。 まずはその中身です。「台湾人、不応該有声音嗎?」で始まる「非常報導」はVCD一枚が約一時間のテレビ番組の形式を取っていて、ミス・ユニバース台湾代表で国名を使えない悔しさを味わった経験を持つという(『新台湾』399 号)陳思羽が番組の主持人を務めます。特報番組風に資料映像を用いながら、統派政治家と統派媒体のジャーナリスト(と見做される人々)が名指しで批判され、それを受ける形で安迪や彭祥瑛ら俳優による漫談風の掛け合い、街角の政治談議、風刺劇などが続き、最後に各党の立法委員を評価する「政治五燈奨」で終わります。とくに宋楚瑜、邱毅ら親民党政治家、そして陳文茜など政論番組の主持人たちの行状が、私生活にも踏み込んで辛辣に批判され揶揄されます。ただ取材に基づく新しい情報があるわけではなく、台湾語を用いた掛詞や皮肉を交えながら民衆が本音をぶつけるといった趣です。一方「政治五燈奨」は、台湾政治通を自認する魔鏡夫人が参加者の意見を聞きつつ政治家を評価するというもので、こちらの方は経歴や実績などそれなりの根拠を示しつつ分析がなされます。第四集まででは3点が最高で、民進党の議員は2(有待努力)から3(表現良好)であるのに対して、親民党の議員には1(絶対不適任)や1.5(不適任)といった厳しい評価が下されます。いっぽう国民党議員への評価は0から3まで様々で、すべて否定的というわけではありません。 次に流通の仕方です。この種の話は確実なことが分からないのは仕方ないとして、複数の報道をつなぎ合わせると、「非常報導」はもともと阿扁支持派の学生が作ったものを元に、主流媒体の「偏藍」ぶりに不満を持つ若手のマスメディア関係者が手を加えて製作したもので、台視や民視に放映を打診して断られた後、南社の協力を得て南部各地で上映と販売を行ううちに話題を呼ぶようになり、やがて北部でも流通するようになったということです。しかし大量に出回る「商機」を作ったのはむしろ邱議員の行動と台北市政府による取締り、そして事の成り行きとVCDの内容を全国民に伝え続けた主流媒体だったと言えます。騒ぎが大きくなってから VCDはコピーを含め多様なルートで流通しました。正版は『台湾日報』に入手方法や出荷状況が載りますが、入手先が限られ、数にも限りがあるため短期間で無くなるようです。そのほか『新台湾』には第一集の引換券が付いていましたし、『八卦王』という雑誌が出所不明の第三集を付けて販売し、その社長がちょっとした有名人になるというエピソードもありました。コピー物は光華商場付近のほか、駅前や夜市など人通りの多いところで売られています。私の最寄りの捷運双連駅にも、VCDの箱を積んだバイクや番組のテーマ曲を流すミニバンが来ていました。大体二枚セットで150元から200元でしたが、時が経つにつれ売値は下がってきています。11月下旬に街角で見た限りでは、次々と売れているというわけではありませんでした。 そして紛争と論争。まず藍営側は、「下流、低級」と嫌悪感を露にした宋党首をはじめ親民党が激しく反発しましたが、マスメディアで表に出てくるのはもっぱら、自分が関係者と見做した人々を片っ端から訴えた邱毅議員で、怒ったり泣いたりのまさに独壇場でした。謝志偉氏らの黒幕説には証拠を見出せずに逆に邱議員が謝罪する結果にもなりました。これに対し緑営側は、独派諸団体に加え台聯が積極的に擁護していますが、民進党は一定の距離を置き言論の自由など原則上の支持に止めています。また週刊誌の『新台湾』『Taiwan News』、日刊紙の『自由時報』『台湾日報』といった活字媒体が擁護の論陣を張っています。基本的な主張は、民主国家の言論の自由の範囲内である、三年半も陳水扁を罵り続けた人間が、たかが数分批判されたくらいで過剰反応である、統派媒体が締め出してきた民衆の声の現れである、といったものです。一方、名指しで批判された「統派」政論番組の主持人たちは概ね平静を保っていますが、陳文茜などは腹に据えかねていることが彼女自身の番組からも伺えます。テレビ局自体は、「統派」批判に正面から答えることはせず、当事者間の争いを報じ討論番組の話題に載せることで視聴率を稼いでいる感じです。 最後に、とりあえず現時点において、この事件は何をもたらしたのか。選挙に関して言うとVCDの内容そのものは選情を大きく左右するものではないと思います。現在拮抗している藍営・緑営の支持率は、すでに明確な支持政党を持つ層の数字であり、これに票を上積みできるかは中間選民の取り込みにかかっているとよく言われます。しかし「非常報導」は取材に基づいて何か新しい事実や側面を明らかにするというより、主流メディアに載らない民衆の本音や不満を吐露するという性格のものであるため、既存の価値観の強化、つまり緑の人は共感し、藍の人は嫌悪を強めることにはなっても、中間選民を改めて納得させるような要素は見当たりません。ただ選挙とは別に、言論の自由をどう解釈するかについて、藍営と緑営の価値観の差を浮き彫りにした面はあります。少々度を越した批判も民主国家にはつきものであり、名誉毀損と言えるほど酷ければ時間をかけてでも司法の判断を仰ぐしかありませんが、藍営を担う人々には批判を許さない権威主義的姿勢が確かに見られます。例えば台北市当局の取締まりは、厳密に言えば表示に問題がある媒体などいくつも出回っていることを考えると、やはり選択的で、なぜ今回の取締まりに限って迅速かつ厳密だったのか不自然との印象が強く残りました。 また別のところでこの事件は被害者を生み出しました。本来政治的立場とは関係ないはずの出演者たちが、訴訟を含む政治世界からの圧力に曝され、私生活でも脅迫や嫌がらせを受け、出演者の一人は自殺を図ったと報じられました。芸能界の事情について私はよく知りませんが、不適切な言動を理由に演芸工会が安迪の除名に動いたのには驚きました。結局見送りになりましたが、同業の会員を政治的圧力から守るのとは全く逆の圧力がはたらいたわけで、台湾の芸能界には国民党時代の権威主義が強く残っていると語る台視の江霞董事の言葉(『新台湾』400号)に説得力を持たせる出来事でした。こうした状況の中で台聯が「非常報導」出演者支援のためのイベントを企画したり、造勢活動に呼んだりしています。はじめ弱気だった安迪氏ですが、いまや独派の闘志として目覚めつつあるようにも見えます。 11月25 日、台湾媒体革命工作室負責人の廬統隆、製作者の何志能といった人々が表に出てきて製作の背景と経緯を説明しました。まだ十分に人々を納得させてはいないものの、謎めいた部分が薄らぎ、とりあえず事態は沈静化に向かっているようです。もっとも、十何集分かを撮り終えているということで、このあと第五集以降が出回るはずですし、新しい事実が判明してまた何か展開があるのかもしれません。このところ新聞や雑誌で飛び交っている「非常~」という表現も、まだ当分は使われることでしょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第5回 食の台北(2003年12月19日) 西暦2003年はもう残りわずかですが、春節までまだ日がある台湾の年末は、淡々と過ぎていきます。日本からのメールに添えられた「良いお年を」という言葉に、年の瀬を感じる程度です。さて、今日は少し趣向を変えて、食の話題と行きたいと思います。文献を読む気がしない日はあっても、食事ばかりは毎日欠かせないだけに、半年いればそれだけ食生活の経験も積むことになります。伝統的なものも外来のものも、外食産業の発達した台北での生活は、やはり持ち帰りや外食が中心になっています。大半の料理が「外帯」を前提に作られる台湾の食には、日本のような「手抜き」の響きはあまりなく、むしろ持ち帰りをしてこそ楽しめるとも言えます。最もよく利用するのは何十種類ものおかずの並ぶ自助餐の類で、店ごとの得意分野や出来たての時間帯というのがあって、うまく利用すればなかなか楽しめます。とはいえこればかりでも飽きるので、魯肉飯、お粥、麺、水餃、肉包、割包、肉粽、漢堡と試しているうちに、レパートリーはそれなりに増えていきます。 ガイドブックに載るような店も手頃な価格で気軽に寄れる所がほとんどなのでよく利用します。日本のガイドブックの情報の充実ぶりは台湾人も感心させるほどで、これにインターネットの情報も含めると、とくにここ数年、台北の食の楽しみ方は見事に網羅されマニュアル化されています。ただ、台北は食の天国とばかりに、ガイドブックがどの店も褒めているのはちょっと不満で(インターネットは比較的シビアですが)、実際にはがっかりすることも少なくありません。また地元の情報誌に載る西式や日式の食べ物は、日本人の一般的味覚からするといただけないものが大半です(うどんのようなパスタ、バター漬けの菓子パン、激しく甘いケーキ、大味で甘い日本料理…)。しかしそれはともかく、台北には確かに豊かな庶民の食文化があり、美味しい発見があります。挙げるときりがないので、今回はそれらの中から二つだけ取り上げてみます。 まずひとつ目は「小籠包」です。言うまでもなく皮の中に熱いスープと具が入っている点心ですが、もともと上海あたりの料理であるせいか名称はまちまちで、小籠湯包と称しているところもあれば、小籠包をさらにスープに浸して食べる料理をとくに小籠湯包と呼んで区別している店もあり、蒸籠に小さめの肉包を並べたものを小籠包として出す店もある(これはがっかりします)といった具合です。学生の頃に旅した上海で気に入って以来よく食べる料理のひとつなのですが、台北の街角にもあちこちにあり、店ごとに解釈が違っていて面白いので、新しい店を見つけるたびに試しています。中のスープは火傷するほど熱く、しかし冷めると味が落ちるため、タイミングが大事ですが、台北の人は湯匙を使いながら薑絲と一緒に上手に口に運んでいきます。 台湾の小籠包を有名にしたのが「鼎泰豊」(信義路本店、忠孝東路支店)であることは今さら言うまでもないことでしょう。確かにスープの味といい、薄い皮といい、仕上がりの美しさといい完成度が高く、いつも観光客で賑わっていますが、客の捌きも効率的で、味が落ちないところは感心します。しかし鼎泰豊で修行をした料理人が開いたという「京鼎小館」(敦化北路)と支店の「京鼎楼」(長春路)も、味付けを受け継ぎながらも特色を出しています。ここの小籠包は大きめですが崩れることなく薄い皮に納まっていて、スープの味付けがやや濃くコクがあり、これを口に入れたときは幸せな気分になります。何度も行っていますが飽きることがなく、個人的にはここの小籠包が一番美味しいと思います。一族総動員といった雰囲気があり(皆さん顔がよく似ています)、京鼎楼の方では小籠包を作る工程を間近に観察できます。ちなみにここは「豆沙小包」も絶品です。 もうひとつ鼎泰豊の流れを汲む店として「上鼎豊」(南京東路)があり、こちらはさらに小ぢんまりとした庶民的で素朴な店で、若い老?が一人で切り盛りしています。皮が厚くすこし無骨な小籠包ですが、味はやはり鼎泰豊系のそれです。その他の店としては「陶陶」で修行をしたという「明月湯包」(基降路)の小籠包も美味です。ただこちらは、全部つながって出てくるパリッとした鍋貼の方がお薦めかもしれません。もちろん、こうした名のある店でなくとも、街角の屋台でそれなりに美味しく食べられます。一般に小籠包の値段は、十個で一籠が百元を切るものから百元台後半までですが、値段と味は概ね比例しているように思えます。それだけに、街角の小さな店や屋台の小籠包が美味しいと得をした気分になります。 そして屋台と言えば、このところよく買うようになったものとして「滷味」があります。これは基本的に持ち帰りですから、小籠包のようにガイドブックの探索の対象にはなりません。鶏肉、豆腐、卵、昆布、野菜、麺などの食材を積んだ滷味の屋台もまた、街の至るところにあります。ただほとんどの食材が煮込んだ茶色をしていて見栄えは決して良くなく、鳥の頭や足先まで並んでいてグロテスクにも見えます。注文の仕方が分からなかったこともあって、来た頃は通り過ぎるだけでした。しかし一度試してみると意外な美味しさで、それ以来頻繁に利用するようになりました。滷味の屋台では、材料を自分で籠に入れ、調理方法(煮る、焼く)、切り方、薬味(鹹菜、葱)、辛さなどを指定しながら作ってもらい、ビニール袋に入れて持ち帰ります。店ごとにかなり味付けが違うので、好みの屋台を見つけ、好みの調理方法や薬味を見出すのがポイントになります。 滷味は日本人的に言うと、最高の「ビールのつまみ」に違いないのですが、この感覚は日本の食文化を通した解釈のようで、ビールと一緒に食べている人を見ませんし、飲み物を売っていてもお茶やジュースだったりします。客層にしても昼間は主婦、夕方は学校と補習班の合間の学生(マクドナルドに持ち込んで食べている人も見ました)、夜は仕事帰りのOLやサラリーマン、夜中はカラオケ帰りの客やチンピラ風の男性と、老若男女を問いません。滷味は屋台以外にも色々なところで売られているのですが、パン屋にまで置いてあることがあって、これはパン屋に焼き鳥が置いてあるようで、どうもミスマッチに思えます。いずれにせよ、日本人としてはやはりビールと結び付けたくなる味なので、よく夜食に滷味を買い、コンビニでビールを買って帰ります。 持ち帰りはいまやすっかり生活の一部となり、煮る滷味はここ、焼く滷味はここ、肉包はここ、お粥はここ、貢丸湯はここ、柳丁汁はここ、と調達のパターンが出来ました。大都市の真ん中でこういう楽しみがあるのは台北ならではです。ところで屋台の老?には女性が多いという印象を受けます。知り合いの台湾人女性に話したところ、そういう女性には、檳榔を噛んで賭け事に明け暮れるだらしない男性が付いているものだ、と義憤をこめて力説していました。どこまで実像なのか分かりませんが、彼女らは確かに長時間、実によく働いています。自宅の脇にある屋台でも女主人が仕切っていて、居るのか居ないのか分からない男性たちは指示されないと動かない脇役です。そんな光景をみていると説得力があるような気もしてきました。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第6回 台湾の「區域研究」(2004年12月30日) 春節は、除夕間近の迪化街の買出しをはじめ、初一の龍山寺の人波や、鳴り響く爆竹や花火の音など賑やかな雰囲気を味わいましたが、やはり全体としては街の多くの機能が停止し、里帰りで人が減った台北は静かなものでした。11年ぶりの寒波と連日の雨で、観光地の人出もいまひとつだったそうです。私もほとんど家にいて、編者として関わっている地域研究の入門書の原稿がちょうど出揃ったところだったので、それを読んで過ごしました。この仕事自体は台湾と直接関係はないのですが、今回の滞在は地域研究のあり方について考える良い機会にもなりました。その一つのきっかけは中央研究院で進められている地域研究(こちらの言葉では「區域研究」)に接したことで、なかなか興味深い発見もありましたので、今日はこれを取り上げたいと思います。 すでに佐藤会員の台北便りで紹介されていたように、中央研究院の人文社会科学系の研究機関はディシプリンごとの構成へと組織再編が進行中です。台湾の社会学界を担う中核的研究者が勢揃いする社会学研究所ですが、民族学研究所から分かれ、籌備處を経て正式に発足したのはまだ数年前のことです。いまも民族所の建物に間借りしている状態で、そのうち独立した建物に移るそうです。一方、政治学の方はまだ政治学研究所籌備處が発足したばかりです。しかし遅かれ早かれ、既存の経済学(経済所)や人類学(民族所)に加え、社会学、政治学と主要ディシプリンごとの研究体制に再編の方向にあります。私の専門は政治学で民主化や市民社会が主な関心領域なのですが、今回の滞在では蕭新煌、張茂桂、范雲といった各世代を代表する社会運動研究者のいる社会所に受け入れてもらい、実際これらの方々にたいへんお世話になっています。 その民族所兼社会所の建物の中に、もうひとつ社会所の蕭新煌氏を中心に運営されている「亞太區域研究專題中心」(Center for Asia-Pacific Area Studies,CAPAS)があります。アジア太平洋(東南アジア、東北アジア、太平洋島嶼)地域に関して学際的研究プロジェクトを実施する機関で、中研院各所から関連分野の研究者が集まって共同研究を行うほか、研究成果の出版(書籍・ワーキングペーパー・雑誌)、研討会や講演会の開催、若手研究者支援など積極的な活動を行っています。蕭新煌氏は国策顧問としてお忙しい身ですが、同専題中心の活動には相当力を入れていて、行政人員の方々の効率的な仕事がそれを支えています。私もこれまでいくつかの国際研討会(「台灣與南韓的社會運動與民主鞏固/Social Movements and Democratic Consolidation:Taiwan and South Korea Compared」、「Prioritizing the Middle Class Research in Asia-Pacific」)や講演会(石井米雄・神田外語大学学長「The Kyoto Experience in Establishing Southeast Asian Studies in Japan」、王賡武・シンガポール国立大学東アジア研究所所長「東南亞研究新發展」)に出席しました。 簡単に振り返ると、台湾と韓国の政治・社会比較は近年流行りの二国間比較ですが、若手を中心に両国の現地の研究者による直接対話であった点が面白く、アジアの中間層の国家横断的な研究は、周知の通り蕭新煌氏が長年取り組んで来た研究の延長線上にある豊富な内容でした。また外国のアジア地域研究を担ってきた指導的研究者の経験を聴く二つの講演会では、講演を受けて台湾各地の研究機関からの参加者がそれぞれの実情などを語り、台湾の地域研究のあり方についての議論となって盛り上がりました。どれも規模がそれほど大きくないこともあって、打ち解けた雰囲気の中で、アジア各国と台湾の研究者が双方向的に交流する場となっていました。台湾の地域研究に対する台湾人自身の評価はというと、研究・教育機関が少なく専任スタッフの数もまだ限られていることや、言語トレーニングの体制が整っていないこと、予算の獲得の困難さなどが指摘され、概ねまだ発展途上との認識です。関連文献やホームページを散見した限りでの私の印象もだいたいこれと一致します。 しかし台湾の研究環境には日本では得難い要素もあります。まず一つとして、研究会の参加者本人が東南アジアの華僑であったり、親戚がいたり、滞在経験があったりといった事情を背景に、意見や情報が出されて議論が盛り上がる場面が幾度かありました。王賡武氏も指摘されていたことですが、華人ネットワークは台湾の東南アジア研究の発展にとってひとつの重要な資産となり得るでしょう。そしてもう一つ、うまく表現するのが難しいですが、東アジアと東南アジアの重なるところにある台湾の持つ「研究の場」としての意味合いが挙げられます。地理的に両地域の間にあるというだけでなく、社会的にも文化的にも双方の要素が混じり合う台湾は、特色ある研究拠点となり得るように思えます。 まず東アジアの一部としての台湾については、中国との関係という政治的要素が関わってきますが、ここではとりあえず今日まで続く歴史的な人と文化の往来からして明らかなことと考えておきます。そして東南アジアについては、先に述べた華僑ネットワークに基づく各国とのつながりに加え、フィリピンやベトナムを隣国に持ち、そこから多くの人々を生活者として受け入れている現実があります。それに、他の研究者とも話したことがあるのですが、台湾では特に南に行くほど気候風土だけでなく習俗や社会のあり方に、おそらく東南アジア的と言える要素が見出されます。さらに台湾には、太平洋島嶼の流れを汲む先住民族の存在があります。このように周辺地域の複数の要素が、歴史的にそして現在進行形のものとして融合し内化されている台湾でアジア太平洋研究が行われるとすれば、それは日本の地域研究の根底にある「他者の理解」とは一味違う、現実味を帯びた「近親者の理解」という態度も併せ持って発展していくのかもしれません。台湾の地域研究に接してのごく初期的な感想にすぎませんが、このような考えにいたりました。 さて、最後にCAPASの話に戻りましょう。ここで開催される研討会や講演会は基本的にオープンで、Eメールで登録するだけで参加可能です。ほとんど「要報名」ですが、これは敷居が高いのではなく、全員分の資料と食事の準備のためで、大学院生も大御所の先生も同様に歓迎して振舞ってくれる「好客」な理由からです。CAPASに限らず中央研究院の学術イベントは、研究会の後にもお茶やお菓子とともに歓談できる状況がセッティングされるのが嬉しいところです。CAPASでは今年の春以降も、台越関係の回顧と展望、台湾の韓国研究、台湾の東南アジア地域研究、台湾の日本研究、アジアの民主再考と各種の研討会が予定されています。台北に行かれる予定があって関心のある方は参加されたらいかがでしょう。詳しくは随時ホームページ(http://www.sinica.edu.tw/~capas/)に載ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第7回 勝負師阿扁(2004年3月5日) 2月の中旬から急に春らしくなり、上々の天気が続くなか、総統選挙に向けた両陣営の造勢活動はますます盛り上がりを見せています。この月はテレビでも、史上初の総統候補者の討論(14日)、第二回討論(21日)、副総統候補者の討論(28日)、公投をめぐる討論(29日)と、毎週末イベント続きでした。そして台湾の北端から南端まで手をつないで中国からの武力の威嚇に対抗する「二二八手護台湾」活動も行われました。初の政党輪替が実現した前回選挙に比べて盛り上がりに欠けると言われますが、初めて台湾の選挙に接する身としてはたいへん賑やかな選挙戦に映ります。とくに造勢会は、会場周辺に選挙グッズの売店と香腸や檳榔の屋台が並ぶ縁日的な雰囲気の中、大音響で音楽や効果音が流れ花火が上がる派手な演出で、癖になる面白さです。 最近見に行ったものとして、台北県中和市(2月21日)と基隆市(2月26日)の民進党の造勢晩会があります。小学校が会場となった中和の造勢会では、地元党関係者の挨拶と演説が小一時間続いたあと、党のアイドル的存在である邱議瑩立法委員が司会を務め、蘇貞昌県長がお馴染みの「衝衝衝」の掛け声と全身を使う語りで台北県の発展と陳政権の政策路線の深い関わりを強調し(この人が来ると本当に場が盛り上がります)、続いて呂秀蓮副総統が淡々と民進党政権の歴史的意義を語り(掛け声があまりないので勢いのついた参加者は少々所在なげな様子)、いよいよ阿扁登場です。二二八手護台湾と公民投票への参加を訴え、連戦候補の政策の問題点や矛盾をつき、最後に「相信台湾」の合唱で終わる頃には、すでに4時間近くが経っていました。ほとんどが台湾語でしたが、新聞やニュースを見ていれば大まかなことは理解できます。しかしこのようなイベントは演説の内容以上に雰囲気です。その意味で民進党には、聴衆を引き込んで乗せていく技術に長けた、キャラクターの濃い政治家が少なくありません。 基隆の造勢晩会の方は街の中心からやや離れた駐車場が会場でした。藍が優勢な地域ですが、この日は緑の旗を持った人や遠方からのバスが行き交い、乗ったタクシーの阿扁帽を被った若い運転手に「わざわざ来てくれて」と礼まで言われました。基隆でも蘇貞昌、呂秀蓮と同じ顔ぶれが話してから、阿扁登場となりました。この演説では出版されたばかりの連戦候補の著書を引用しつつ、両岸関係に関する過去の発言との食い違いを執拗に取り上げて批判していました。相手側の動きの細かいところまで把握して迅速に攻め所を見つけるところは元弁護士としての切れの良さを感じました。そして相信台湾の歌で会が終了するかと思われたところで、なんと阿扁自身が舞台から降りて支持者と握手を始めました。やがて、この辺にも来るぞという声が聞こえ、セキュリティーの人たちが道を開けるように指示を始めました。まったく思いもよらなかったことですが、私も握手ができました。最後は支持者に囲まれて揉みくちゃになりながら会場を出ると、ウインドウ・ルーフから身を乗り出して笑顔を振りまきながら去って行きました。 このように造勢会は実に楽しみ甲斐のあるイベントなのですが、ただ参加者の大部分を中高年層が占め、若者とくに学生が非常に少ないことにも気付きます。このあたり「扁迷」が活躍していた4年前とは大きな違いなのでしょう。しかし「手牽手」二二八手護台湾の方は、若者を含む広い層の参加があった点で通常の造勢活動とは少し違っていました。この日は家族・親戚ぐるみで参加する友人と忠孝復興捷運駅近くで合流しましたが、昼過ぎには参加者が沿道を埋め、あちこちで「台湾」「台湾YES」「阿扁凍蒜」が連呼され、車道を通る緑の旗を掲げた車やバイクとも声を掛け合っていました。老若男女を問わず人が「湧いてくる」感じで、その中には大学の支援団体や、二十代のカップルも少なからずいました。歴史的事件としての二二八の持つ重いイメージを前面に出さず明るいイベントにしたことが受け容れやすさにつながったのかもしれませんし、忠孝東路という場所柄もあったのでしょうが、理由は何であれ若年層を引き込んだことはひとつの成果だと感じました。主催者側は登録者が120万人、登録なしの参加者が80万人、合わせて200万人が参加したと発表しています。 一方連宋陣営は、二二八に向け二週間にわたって2000キロを走破する「手連手」路跑活動を展開し、この間、藍軍で好感度ナンバー1の馬英九台北市長と王金平立法委員長が藍のTシャツを着て走るTV広告が頻繁に放映されていました。路跑活動自体は地味でしたが、二二八当日には連宋陣営も高雄と台北で大集会を開催しました。連宋側の造勢会はテレビ中継などでは時々見るものの、現地で見る機会がこれまでなかったので、台北の晩会に行ってみました。台北市・台北県のあらゆる地区から動員された10万人の支持者が中正紀念堂を埋めつくす場景は壮観で、光や音の効果などもよく計算された完成度の高いイベントでした(もっとも終盤になると総統候補の演説中に帰ってしまうグループもいて綻びが目につきましたが)。先に取り上げた民進党の地方都市での造勢会とは性格が異なるためそのまま比較はできませんが、総統候補の登場というクライマックスの雰囲気を比べる限りでは、「支持者を盛り上げる」陳水扁と「支持者が盛り上げる」連戦という違いは明らかであったように思えます。連戦候補も4年前と比べてずいぶん主動的に事を運ぶようになり、演説も上手くなってテレビ討論では予想以上の健闘をしたと評価されていますが、もともと口水戦に向いている人物とは思えません。その点で「泣き」や「下跪」もある宋蘇瑜副総統候補の方は強烈ですが(この日も涙を流しながらの演説でした)、最近は主役である連戦氏がもっぱら前面に出ています。もちろん、造勢活動はあくまでも選挙の行方を決める一つの要素であり、有権者が今回どういうタイプの人物を選択するかはまた別の話です。 ところで、総統選挙そのものが賭けの対象になっていて摘発されたと新聞が報じていました。これだけの接戦ですから賭けの対象としては格好のネタなのでしょう。それはともかく「賭ける」という行為は台湾人の行動を支配するひとつの強い要素ではないかと時々考えます。街角では香腸の屋台にどんぶりとサイコロが置いてあって老板に勝つともう一本貰えるというのがありますが、去年の夏マクドナルドのキャンペーンでも採用されていて、セットを買うとサイコロを振らされました。このいわゆるチンチロリンは、新年には家族で楽しむ遊びでもあり、なかなか盛り上がります。また台湾では、株をやる人の多さと情熱にも並々ならぬものがあり(ファーストレディー呉淑珍までやっているとは思いませんでした)、それを反映してケーブルテレビには無数の関連チャンネルがあります。そもそも独立心の強い中小の企業家が活気のある経済を作り上げてきた台湾です。まさに人生は賭けです。成功者は思う存分胸を張り、相応の肯定的評価を受けます。安全志向の今日の日本人とはある意味対照的かもしれません。言うまでもなく選挙は、候補者のそして主権者の人生を左右する大きな賭けです。台湾人の選挙好きには、賭けに対するこの積極的な姿勢が関わっているような気がしてなりません。 そして選挙を戦う陳水扁の姿こそ最高の勝負師と呼ぶに相応しいのではないでしょうか。いつも笑顔で人の良さそうな風貌のこの人物が「選挙の天才」などと呼ばれるのが、台湾政治を学び始めた頃にはどうもピンと来ませんでしたが、いまや選挙戦を目の当たりにしてこの初期のイメージは完全に逆転しています。大量得票で当選した市議会議員や立法委員選挙はともかく、県市首長以上となると(1985年台南県長選、94年台北市長選、98年台北市長選、2000年総統選)、陳水扁氏は楽に勝てる選挙というのを経験していません。しかも勝利を収めた94年台北市長選と2000年総統選は、「棄保現象」すなわち勝ち目のない候補者の支持者が別の候補に乗り換える戦略投票に助けられての当選です。今回も連宋ペアが成立した昨年4月以来、明らかな劣勢のなかで始まった選挙戦でした。しかしそれでも悲観的な表情などまったく見せず、次から次へと新たな戦いの場を作り出し、笑顔で挑んでくる(相手にとっては不気味でしょう)不屈の精神、総統としての仕事に加え毎晩大衆を相手に複数の造勢会をこなす体力、このタフで頭の切れる陳水扁という人は、国一番の秀才であると同時に、国一番の勝負師ではないでしょうか。いずれにせよ、勝負が決まるまであと二週間ほどです。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第8回 総統選挙とその後(2004年3月31日) 台湾滞在の最終月は、いったん帰国した後に選挙戦を見に戻ってきたため半月ほどしかいられませんでしたが、その短い滞在の間に予想外の出来事が次々と起こりました。選挙が終わったら「謝票」を見て帰国しよう、などと考えていたのが、それどころではない事態を目にする結果となりました。事態はまだ決着しておらず最終的な判断ができる状況にはないので、あくまでも現時点での個人的な体験や感想として、事の成り行きを振り返ってみたいと思います。 藍緑双方が支持者の大動員を行った13日にピークを迎えた選挙戦は、その後とくに大きな動きもなく投票日前日を迎えました。私はこの19日の午後、中央研究院社会学研究所での研究報告を終えて部屋を出たその時に「陳水扁が撃たれた」と聞かされました。テレビの前に集まった研究所の人々の間には、憶測を言うことも憚られる重苦しい空気が漂っていました。テレビでは陳総統・呂副総統の容態と事件現場の状況が刻々と伝えられ、やがて命に別状のないことは明らかになりましたが、国安機制が発動され緊張した状況のなか、両陣営とも造勢晩会は中止となりました(もっとも、行き場を失った支持者は街に繰り出して気勢をあげていましたが)。一方テレビでは陳文茜議員が陰謀説を唱え、蘇貞昌競選総部総幹事が人間性の欠片もないと憤り、疑念を晴らすべく陳総統の傷口の写真まで公開される異様な情景が繰り広げられました。 20日の投票は静かに進行しましたが、夕方から始まった各局の中間集計の結果が二転三転する緊迫した状況が続きます(それにしても局によって集計経過が違いすぎました。総投票数を上回る数字を出してしまった局や、最後に慌てて辻褄を合わせたような局もあって、テレビ局の集計システムのいい加減さを露呈しました)。そして3万票ほどの差で陳水扁候補の勝利が確実となった直後、支持者の前に現れた連戦候補が不公平な選挙だと述べ、選挙の無効を求める運動を開始すると宣言して競選本部で座り込みを始めました。一方、陳陣営の競選本部には大量の支持者が駆けつけ、夜の台北の街に繰り出して歓声を挙げていましたが、深夜から事態は新たな方向に動き始めます。各地の連宋支持者が投票箱の差し押さえを要求し地検署に詰めかけて暴動寸前の状態となり、高雄で邱毅議員の乗った宣伝カーが柵に突っ込む姿や、台中で群衆の中に入って必死で宥める胡志強市長の姿がテレビに映し出されました。翌日から総統府前の凱達格蘭大道は、集結した藍営支持者が票の数え直しだけでなく、陳水扁政権に対するありとあらゆる不満と非難と中傷をぶちまける場と化していきます。藍営の政治家たちが次々と壇上に立って群集を煽り立て、不法占拠に当たるとして退去を求める馬英九台北市長の声は掻き消されました。 結果がこれだけ接近していましたから、票の集計をめぐって異議が唱えられ、票の数え直しを要求する声があがるのは、理解できることです。前回の米国の大統領選でも起こったことで、改善の余地があるのは間違いないにせよ、これ自体は台湾に民主主義があるかないかという話ではありません。藍営の政治家と支持者のやりきれない感情も分かります。陣営内部の仲間割れから政権を失い、これまで経験したことのない野党の地位に甘んじてきた無念さ、民調では連宋やや優勢という結果が大半で勝利への期待が高まっていたこと、それが直前の総統銃撃事件で陳候補に票が流れたと考えられること、そして最後には僅差で敗北したこと。これらが積み重なって悔しさの感情が爆発することも、分からないことではありません。 しかし今回事態を混乱へと導いた最大の原因は、一部の政治指導者にあったように思えます。連戦候補は、まだ正式な開票結果が公表されない時点で、明確な根拠を示すことなく、漠然と公平な選挙でないと述べて、選挙の無効化を訴えて運動の開始を宣言し、事実上支持者の感情に火をつけました。その後は議員たちが民衆を引き連れて地検署や中選会に押しかけ、そこで怪我人が出て建物が破壊されました。にもかかわらずこれらの政治家は民衆の自発的行動は抑えられないと、人ごとのような発言を繰り返します。法的手段に則って行えば異議申し立ては正当な行為のはずですが、混乱を作り出すことで当局に圧力を掛け目的を達成しようとするのは、民主制度を支える法治国家の否定です。合法性など意にも介さないこれら政治家の行為、責任感の欠如には唖然とさせられました。開票終了直後には、マイクを向けられた若い支持者が、意気消沈しながらも選挙の結果は認めるしかないと発言していたのを見ましたが、騒ぎが大きくなる中でこうした声は表立って聞かれなくなりました。陳水扁支持者も当選を喜ぶ雰囲気ではなくなり、沈黙するようになりました。 もっともこれら紛争の現場をマスメディアは集中的に取り上げ過ぎていたかもしれません。数日にわたって総統府周辺に不穏な空気が漂っていたのは確かだとしても、そこを離れると通常通りの人々の生活がありましたし、抗議の続く凱達格蘭大道も一週間を過ぎる頃には緊張が緩んで夜市のような雰囲気になりつつありました。27日の大動員が平和裏に終結し、翌日には抗議の民衆が凱達格蘭大道から退去して中正紀念堂に移ったことで、事態はひとまず沈静化に向かっているように見えます。また藍営の中でも、馬英九や胡志強といった次世代の国民党指導者は、抗議行動を合法的な枠内に止めようと努力した点で、無軌道な政治家とは一線を画していました。民進党は、挑発的行動をとった党員は処分すると警告するとともに、支持者に一定の距離を置くよう呼びかけました。宗教界や経済界からは自制と和解を求める呼びかけがなされました。抗議の民衆の中ですら、暴れ出す人に対しては周りがそれを抑えるシーンが度々見られました。 こうしてみると今回の紛争において、色々なところで自制や抑制の力がはたらいたのもまた事実でした。最後の挨拶に訪れた中央研究院で、今回のことであなたは台湾政治に失望したのではないかと聞かれましたが、必ずしもそうではなく均衡を回復する力が台湾社会にはあると思うと答えられたのは、楽観的に聞こえたかもしれませんが、こういうプラスの側面も見えたからでした。もちろん、国論が二分する状況下で陳水扁総統に課せられた「和解」という課題がきわめて克服困難であることは間違いなく、予定通り2 期目の政権がスタートしたとしても、すべて一人で決めて物事を進めていく陳水扁氏の従来の統治スタイルには再考の必要があるように思えます。いずれにせよ、これ以上事態を深刻化させるような出来事が起こらないことを祈るばかりです。 さて、私の担当する台北便りもこれが最後となりました。 3月の台北はまだ温度の上下はあるものの、汗ばむ日が増え、暑い夏に向かって季節が一巡しつつあることを感じます。SARS危機の続く初夏に始まった台湾滞在は、総統選挙をめぐる紛争のなかで終わりました。約9ヶ月の滞在で出来たことはあまり多くはなく、研究にしても言葉の習得にしても中途半端なところで終わったというのが実感です。ただこれから台湾と関わっていく上での下地がある程度できたという感触は得られました。それに日々の生活体験から選挙戦まで、現地にいてこそ味わえる多様な台湾が経験できました。何もかも新鮮に感じられたので、台北便りの話題には事欠きませんでした。あとで読み返すと訂正したい箇所もありますが、それもまたその時々に感じた現実として、そのままにしておきます。 これらの様々な経験が、多くの人々と知り合うなかで可能になったことは言うまでもありません。その意味で佐藤幸人さんをはじめ日本台湾学会の皆様には感謝の言葉もありません(台湾研究者のネットワークはすばらしいですね)。また台北定例研究会ではお世話になるばかりで、何のお手伝いもできなかったこと、御礼とともに深くお詫びを申し上げます。そして最後に、色々な形で台湾の生活を実体験させてくれた中央研究院社会学研究所の鄭陸霖さんに、心から感謝の言葉を送りたいと思います。彼と知り合えたことで今回の滞在は実に楽しく充実したものになりました。今回得られた多くの人とのつながりを資産として、今後も台湾というこの実に魅力的な国との関わりを続けていくつもりです。 |
|||||||||||||||||||||||||||